講義NO.5 『切実さをアクションする:表現者との協働から眺めるアートマネジメントのかたち』
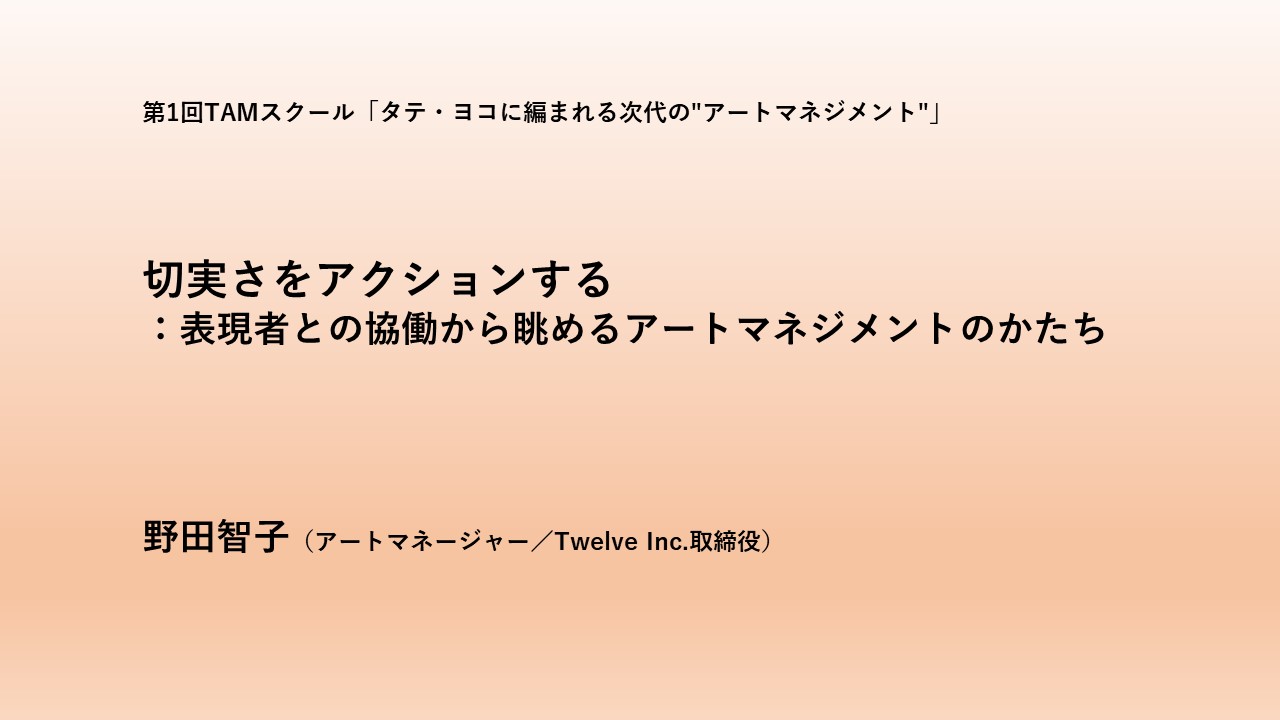
2021年2月1日~3月21日、新型コロナによって活動に影響を受けたアーティストを支援するためにオンライン・アートプロジェクト「AICHI⇆ONLINE」が開催されました。そのプロデュースを担当したのがアートマネージャーの野田智子さん。
これまでさまざまな活動を通じて「切実な問題」に取り組んできた野田さんに、企画立案、運営の考え方について語っていただきました。
アーティストが抱える「切実な問題」。
「大学では写真を専攻していた」という野田さんが、アートマネジメントの世界に入ったきっかけから講義はスタートしました。
野田:大学時代はアーティストになりたいと思っていました。ところがふと、周りの友人たちを見ると、みんなめちゃくちゃいい作品をつくっている。私には彼らのような作品はつくれない。才能がないんだと思いながら過ごしていました。
転機が訪れたのは就職活動。自分の将来を真剣に考え始めたとき、「優秀だった同級生たちは卒業後どうするのだろう」「アーティストってどうやって食べていくのだろう」と疑問がわいたそうです。
野田:それをきっかけに経済活動や社会的立場、さらに生き方などアーティストを取り巻く環境に興味を持つようになり、文化政策を学ぶため静岡文化芸術大学の大学院に進学しました。そこでは国が目指しているような大きな枠組みの文化政策が中心で、ジャンルに関しては演劇やパフォーミングアーツ、音楽ではオーケストラなどが多く、現代アートはほんの少ししかありませんでした。
では現代アートの現場はどうなっているのか? それを知るために、自ら「アーティストと活動する現場をつくろう」と、2006年にアーティストの中崎透氏と山城大督の3人でアーティスト・コレクティブ『Nadegata Instant Party』(以下・ナデガタ)を立ち上げ。ここから野田さんはアートマネージャーとして歩み始めました。
野田:リサーチから対話、制作、発表、資金運用、美術館への収蔵まで、そのすべてをアーティストとともにやっていく実践の場です。各地のアートイベントの現場に入って滞在制作をしたり、コミュニティや訪れた場所にアプローチした作品をつくったりする。これまでに国内外合わせて約30プロジェクトを手掛けてきました。
水戸芸術現代美術センターでは、展覧会場を舞台にした映画のプロジェクトを水戸市民とを一緒に制作、国際芸術センター青森[ACAC]では24時間しか開局しない"24時間テレビ"のパロディ版放送局を手掛けるなど豊富な事例を紹介。
野田:アーティストと共につくっていくことをさらに充実させていくために、ギャラリーなどで働き、美術作品の販売、作家のマネジメント、広報などについて勉強しました。こうした知識を活かせるようになってきたところで、2013年にようやく「アートマネージャー」と名乗れるようになりました。

アーティストを支援するAICHI⇆ONLINE
2020年2月1日から3月21日まで、「AICHI⇆ONLINE」というオンライン上のアートプロジェクトが開催されました。これは新型コロナによって活動に影響が出たアーティストを支援するための愛知県の支援事業です。野田さんは、プロデューサーを担当。愛知とのかかわりはそもそも「2020年までの約7年間、名古屋で暮らし活動をしていたこと」だそうです。
野田:この支援事業は、アーティストたちに一律にお金を配るというやり方ではなく、企画を公募。その企画を通じてアーティストを支援するものでした。そこで私たちは企画チーム「SAAC」をつくり、「AICHI⇆ONLINE」という企画で応募、採択されました。
SAACはSustainable Arts Activity Cooperativeの頭文字をとったもの。メンバーはアーティスト、編集者、webディレクター、アートマネージャー、アートコーディネーターなどで結成されました。
野田さんたちのこだわりが現れているのは「Cooperative」という言葉。これは建築用語の「コーポラティブ・ハウス」という共同集合住宅を意味する言葉からヒントを得たそうですが、共に考え共に活動を行う共同体としてのチームです。
野田:通常のイベントでは、テーマを決めてディレクターを据えてトップダウンで作品をつくっていきます。しかし今回はそうはしたくなかった。今日、明日、何が起こるかわからない、状況がまるで見えない。だからアーティストたちとともに考え、フラットにともに作品をつくっていきたいと思ったのです。ディレクターは据えず、コーペラティヴ(共同体)というキーワードを出し、私たちのことは「企画チーム」といういい方をしました。
「AICHI⇆ONLINE」のコンセプトは3つ。一つ目が「文化をとめない」。2つ目が「今を生きる表現者の発露としてのオンライン・プラットフォーム」。3つ目が「歴史に残る作品群をさまざまなジャンルで生む」だったそうです。
野田:「文化をとめない」をコンセプトにしましたが、実際にアーティストの方たちと話していてわかったのは、表現者は表現することをやめていなかったということ。ただ、表現を届ける先がないだけだったんだと、やっていく中で気づきました。
「AICHI⇆ONLINE」はテーマではなく、スローガンをかかげています。それは『ごんぎつね』で有名な愛知県半田市出身の童話作家 新美南吉の「明日」という誌の一節です。
明日はみんなをままっている。
泉のようにわいている。
らんぷのように点ってる。
野田:新美南吉さんは29歳で亡くなるのですが、この詩は、その少し前に書かれたものです。もっと書きたい──と、泉のようにわきあがる、ランプのようにともり続ける制作意欲をうたったものです。この詩に出会い、テーマよりもはるかに強い言葉、私たちのプロジェクトの創造の意志を表すスローガンとして掲げることにしたのです。
「AICHI⇆ONLINE」には9つのプロジェクトがあったそうです。しかも映画、現代美術、文学、マンガ、音楽など幅広いことが特徴。オーダーは愛知県にゆかりのあるもの、愛知県の風土など、愛知を捉えたテーマで作品をつくることですが、強制はしませんでした。
もっとやりたいことがあれば、そちらを優先して構わないとゆるやかにオーダーしたそうです。プロジェクトの依頼の方法は2つあります。一つは作家に直接依頼する方法。もう一つは、企画者に作家の選定まで含めて依頼するというやり方です。
野田:ウェブサイトの設計にも工夫をこらしています。グーグルマップの愛知の地図上に、プロジェクトで誕生したアート作品の展示場所やゆかりの場所を表示しました。最初は文字が地図の上にのっかっているように見えるのですが、地図をどんどん拡大していくと路上に文字が転がっていたりもして。この文字がピンの機能を果たしているのでクリックすると作品が閲覧できるようになっています。その土地性から作品を見るという楽しみ方ができるわけです。
そもそも野田さんが、このような壮大なプロジェクトに挑戦しようと考えたのは、コロナ禍でアーティストのために何かできることはないのかと、悶々とした日々が続いていたからだといいます。
野田:20年先、30年先の未来の自分に「あのとき、あなたは何してたの?」と問われると思ったことも大きい。また今後も発表の場がオンラインになることも増えていくと思います。どうやればいいのか試してみたいと思ったこともあり、公募にチャレンジしました。
足早に自身の活動とその裏側を振り返りつつ、講義の最後はアートマネジメントをとりまく問題意識を列挙。「このあとのシンポジウムの議題にもつなげたい」と提案してくれました。
野田:あるスキルを持ち、時間を切り売りせざるをえない専門職にもかかわらず、アートマネジメントの仕事は予算ありきで、見積の提出すら求められないことがほとんど。契約期間も極めて限定的になる。渡り鳥のようにしか働けない環境をふくめて、アートマネジメントの労働環境は考え直していく必要があるのではないでしょうか。

オンラインならではの苦労
ここからは、TAMスクールの企画プランナー田尾圭一郎(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社CCCアートラボ事業本部プロジェクトプランニング事業部ユニット長)とのクロストーク。
田尾:コロナ禍でアーティストが表現活動をすることが難しくなったという話は、色々なところで耳にしましたが、そうした中で「AICHI⇆ONLINE」は諦めずに表現活動をした稀有な例だと思います。オンラインならではの苦労を教えていただけますか?
野田:まずはオープンしても反応がまったくわからないことでしたね。通常のアートプロジェクトは、オープニングやプレビューがある。そこにアーティストがいて、作品そのものが目の前にあるし、それを見に来るお客さんもいる。その雰囲気を遠巻きに見ることもできます。しかし、オンラインでは誰がどこで何を見ているのかさっぱりわからない。感想の発露の場はSNSくらいですが、それもまたオンライン。まったく手ごたえがありませんでした。
田尾:鑑賞者の反応を得る方法はその後見つけられたのでしょうか?
野田:インスタグラムでトークライブをしました。終盤は、アーティストリレートークをやりました。9プロジェクトのアーティスト全員に10分くらいのプレゼンをしてもらいました。それでやっと、何人見に来たとか、タイムラインにコメントがついたとか、反応を感じましたが、数字じゃない部分の情報はわかりにくかったですね。
田尾:プロジェクトを立ち上げていく企画運営側での進行面ではいかがでしたか。
野田:企画チームのメンバーとは、一度も会わず、すべてオンラインで進めました。アーティストに対しても、すべて電話かZoomで依頼しました。また、人によってオンラインの得手不得手があるのもわかりました。
田尾:コミュニケーションの手段が増えると、対応もさまざまになりますよね。会話で伝えるのが得意な人もいれば、デジタル・コミュニケーションで文字をベースにしたコミュニケーションが得意な人もいる。いろいろチューニングをしながらその都度最適な対応をしていく必要がありますよね。
野田:あとはコロナで人に会えず、気持ちがふさいだり、モチベーションが下がってしまう人もいる。そういう人の気持ちをあげていくことも大切ですよね。プロジェクトはフリーランスの集まりだったので、プロジェクト以外の仕事の話を共有したり、ミーティングの前に10分間ほどムダ話の時間を設けたり、密なコミュニケーションを意識してきました。あとはZoomで室内が見える場合、背景に映り込む本棚や絵など話題にできそうなものを探しますね。
田尾:「その本、僕も持ってる」といった何気ない話題だと会話をはじめやすいですよね。居酒屋なら「最近、どう?」と気軽に聞けるし、表情からある程度、相手の感情や現状を読み取ることができる。けれど、オンラインだと相手の温度感がわからない場合も少なくありません。
野田:1対1でやっている分には、きちんと伝わるように注意できますが、複数人になれば、一部の人にうまく伝わらず、誤解が生まれることもありますよね。
質疑応答「地域に根づいたオンラインイベントの可能性」
最後に参加者からの質疑応答の時間が設けられました。「AICHI⇆ONLINE」を例に、野田さんの企画立案の具体的なやり方を紹介すると、実践的な質問が集中しました。
たとえば「オンラインと地域をつなげるようなイベントはできないものか」「オンラインイベントにおける場所性についての考え方を知りたい」「グーグルマップに印をつけたように、現地に実際に何か置いたらおもしろいかもしれない」といった具合です。
実際にイベント関連の仕事に従事している参加者の方がほとんどだったため、日々、困っていること、悩んでいること、チャレンジしたいことなどが質問の中心でした。それぞれの持ち場で抱える切実な問題をシェアする機会にもなっていたようです。
2021年8月10日
取材・文:竹内三保子(カデナクリエイト)




