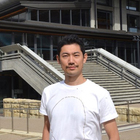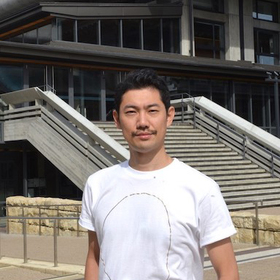これでいいのか!? どうする? コロナ以降のアートマネジメント
オンラインイベントレポート

新型コロナウイルスに対する芸術文化応援プロジェクトとして、2020年7月から4回にわたって実施してきたオンライントークイベント。総まとめとなる今回は、各回に登場いただいた4名の方々が再登場。「コロナ以降、非接触時代のアートマネジメント」をテーマに、①人財、②資金調達、③創造環境、④協業、⑤アートの必要性をどう伝えていくかといった5つのトピックスについて、ジャンルを横断したクロストークをしていただきました。
重なり合うことで見えてきた、アートマネジメントの微かな希望と確かな未来。当日のレポートをお届けします。
コロナ下で気づいた、ケアとトラブルメーカーの重要性
コロナ下でのアート活動や表現について考える場を広く提供したい。
そんな思いから「演劇・舞踊」「音楽」「美術」の各ジャンルで活躍するさまざまな立場、役割の方々に加えて、トヨタ博物館の館長・布垣直昭氏も加えた4名を前にまずは進行役の若林朋子氏が切り出しました。
若林氏:異なるジャンルだからこそ、そこに横串を指すかたちで皆さんと知恵を出し合い、次に踏み出すためのトークをしていきたい
始まりはアートに携わっている「人財」について。本来は「人材」ですが、人はアセットであるとのトヨタの思想をリスペクトして、今回はあえて「人財」という文字を使いました。
「トリエンナーレのような催し、組織を束ねる中で、まさに"人は人財"であると感じた」と切り出したのは、横浜トリエンナーレ組織委員会のプロジェクト・マネージャーである帆足亜紀氏です。
帆足氏:アーティスト、スタッフ、そして、もちろん観客。こういう人財がいるからこそ成り立つ。展覧会やイベントが中止になる中で、こうした人へのケア、それは経済的にも精神的にもだが、その重要性を今回のパンデミックによって気づかされた
一方で今回、オンラインでのワークショップを開催したところ「不便かな」と思いきや、メリットもあったといいます。
帆足氏:今まで遠方であったり、身体的な理由から美術館に足を運ぶことが難しかった方たちに気軽にアクセスしてもらう方法を考えるきっかけになった。いままで通りであれば気づけなかったと思う。そういった側面にもケアが必要だったことに気づくよい契機になった
この話を受けて「ケアするためには想像力が必要であり、これまでにない事態を迎え、ダイレクトなコミュニケーションを削られた今、我々は試されている気がする」とロームシアター京都 プログラムディレクターの橋本裕介氏は語りました。
橋本氏:我々が運営するホール、ロームシアター京都は京都市が設置した劇場なので、行政が示したガイドラインに沿うのが原則。しかし一方で、市の中心となる公共施設でもあるため、周辺の民間の劇場に与える影響も大きい。ロームシアターが活動を縮小すれば、他の小さな劇場も追随せざるをえず、そこにかかわる人たちの暮らしに直結してしまう。我々の劇場もコミュニティとともに存在しているということを想像しなければならない
「そうした組織、マネジメント側の悩みは、アーティストの生活そのものに直結する」とつなげた後、問題提起したのはトヨタ博物館館長で、トヨタ自動車株式会社 社会貢献推進部の部長でもある布垣氏です。
布垣:アートは創作者個人に帰結するので、人財として最もケアすべきなのはやはりアーティストではないか
これを受け、「確かにそうだが、私たちアーティスト一人ですべてが成り立つわけではない。個人がマネジメント側の組織やスポンサードする企業などと有機的で、水平的につながりを持つ組織だと認識している」と作曲家の野村誠氏から発せられました。
野村氏:水平的というと横並びの同調圧力にも見えるが、それは違っていて、多様なメンバーがお互いを認め合うことでそれぞれの個性が活きるようになる。モデレーターという役割があるように、トラブルメーカーという役割の人がいてもいいと思っている。
少しおかしなこと、とがったことを発言する人間がいても「何だアイツ」と排除しない組織。むしろ、そういう意見が出ることで他も意見がいいやすくなって、組織全体が活性化するような...
コミュニティの中でポジティブな起爆剤となる存在。そんなトラブルメーカーは、アーティストこそが担うべき立ち位置なのかもしれません。
帆足氏:アーティストは作品を通して、将来起きうる問題を自然と提起してくれる。だから我々はドギマギしながらも、それに気づかされる。コミュニティの中でそういうことを話し合うきっかけをつくってくれるのがアーティストであり、重要な存在だ
「まさに今、コロナという予測しえなかった新たな事態に直面し、自分の頭でしっかり考える力が問われている」と布垣氏もいいます。
布垣:「何が正解か誰にもわからない時代。しかし周りの目を気にして足踏みしている間に、時は過ぎる。トライ&エラーを繰り返しながら、さまざまな可能性を模索するのが正しい。アーティストはそうした挑戦の後押しをしてくれる貴重な人財といえるだろう
アートを動かす役割は、多岐にわたる。
ポジティブなトラブルメーカーとなるアーティストのような存在がいまこそ必要なのでは──。アートマネジメントにおける人財の話は、そのまま組織運営の話へと続きました。
布垣:トヨタでクルマのデザインをずっと担当してきたところの実感がある。ヒットメーカーと呼ばれるような優秀なクリエイターだけを集めたチームをつくれば、今までにない新車をつくれる。
そう思いがちだが、案外うまくいかない。
優秀なクリエイターは必要だが、その方たちをうまく盛り上げてモチベートする応援団のような人、ふと出たアイデアの欠片を拾ってかたちにしていく人など、多様な役割がいてこそ、組織は機能する。アートマネジメントも同じではないか
野村氏はこの話題から一つ、コロナ下での危機感をたぐりよせます。
野村氏:感染を回避するために、これまであたり前にあったわけのわからない会合や飲み会が減った。よい面もたくさんある。しかし、機能的なオンラインのつながりだけだと、排他的にも簡単になれる。異なるもの同士がつながって何かが生まれるというアートに必要な相互作用が起こりにくくなっているのではないか
頷きながら、答えたのは、座組をする側である、橋本氏と帆足氏です。
橋本氏:コロナが後押しすることかもしれないが、アートの世界は昨今"効率性"を強く求められる。ジョブディスクリプションに基づいて専門領域に強い人を集め、役割と責任を明確にして仕事をしてもらう手法が根づいている。しかし、我々の舞台芸術の世界ではある種の職域によるヒエラルキーができて、水平化を妨げる要因になっているのではないか
帆足氏:そこに懸念はある。役割を決めすぎると、自分の役割しか見なくなり、別の領域の誰かがこぼしたものを拾わなくなりがちだ。それを防ぐために明確なビジョンを掲げて共有し、皆で同じ方向を向くことが欠かせない
さらに話題は人財発掘、開拓へ。コロナ下で浮き彫りになった、声の大きな人、目立つ人にばかりカネや情報が集まり、偏りすぎている面があるのではないか、という課題にトークは移行しました。
野村氏:たとえば助成金のような情報も、本当に必要な人に届いているのか? 今はまだ芽が出ていないけど、未来につながるようなアーティストやプロジェクトを掘り起こせているのか? さきほど布垣氏がいったクリエイター以外の応援団的な人財が不可欠なように、こうした既存のアートの枠を超える人々と情報をつなぎ合わせる存在、新たな才能を見つけだす存在こそ、積極的に育てていくべきではないか
「まさにアートマネジメントとして求められる役割がそれだ」と帆足氏も同意。
帆足氏:私たちのトリエンナーレも「毎回、実績のある作家ばかり」と批判を受けることも少なくない。埋もれて見えづらい作家の参加を否定しているわけではなく、どのようにさまざまな作家と接点を持ち、つなげていくことかと思う
橋本氏:今まさに、助成団体のプログラムオフィサ―の仕事を見直すよい機会だと思う。効率性、収益性だけ意識するのではなく、新しい作品、才能を見出すことにこそ価値がある
自社のものにかかわらず、歴史的な価値のあるものから最新のものまで、数多くの車体、クルマ関連の資料を所蔵するトヨタ博物館の館長としての目線から、布垣も象徴的な話を差し込みました。
布垣:クルマをつくっていたときは、もちろん売れるクルマを目指す。ヒット商品をつくろうとする。ただヒットしたものだけが価値あるものではない。いま博物館の人間として、収蔵する側になると本当にそれを実感する。現世利益と後の価値は、イコールではない。アートマネジメントとなるとなお意識するところなんだと思う。その目利きははずせない
その意味で、新たな才能を引き出し、資金面での支援もうまくつなげるかたちとして、橋本氏より京都市が2020年秋に実施したマッチングファンドについて説明されました。
橋本氏:ふるさと納税型のクラウドファンディングだが、集まった寄付総額と同額を京都市からも上乗せ助成することで、集まった額の2倍が文化拠点支援にあてられる新しい取り組みだ。「京都市がお金を出す=お墨付きを与えている」プロジェクトということで、一般の方からの寄付を誘発することができた
このプロジェクトへの寄付は、一般の方はもちろんのこと、企業へも波及、メディアにも取り上げられました。その結果、寄付を行った企業も注目されることとなり、さまざまな効果を生み出しました。
アートにかかわる人財の多様性が強みになるのと同様に、資金面でも多様なスタイルが必要なのだと印象づけました。
時代を超えて価値を紡いでいく。
コロナ下でイベントの来場人数が制限されるようになり、来場者数を追求することが難しくなりました。その結果、むしろアートの本質的な価値を追求するということに回帰するきっかけとなったのではないでしょうか。終盤はそんなアートの本質の話へ。
まず劇作家である故・太田省吾さんの言葉が橋本氏より紹介されました。
橋本氏:アートを考える際には時間を3つの層で考える必要がある。「日々」「時代」、そして「永遠」。この考えを知ってから、日々の生活である日常を時代へどうつなげていくのか、そして自分が亡くなった後の時代に何を残せるのか。劇場に携わるようになって、それを考えながら仕事をするようになった
布垣氏からは、欧米と日本での「クラシック」という言葉の使い方の違いを感じたエピソードが語られました。
布垣:欧州に住んでいた際に、とある場で手掛けたクルマを"クラシック"と評された。"古い"という意味で捉えてしまった。しかし、本来は『時代を超えた価値がある』と最上級に近い褒め言葉だそうだ。最近の社会は消費型で流行り廃りを意識しすぎる。それはアートも含めてだ。専門家はもちろんのこと、一般の方も、時代を超えて価値のあるものを大事にする目を持つべきではないか、そうすることで経済の循環も変わっていくのではないか
それに対し若林氏より「自分が本当に大事にしたい価値あるものは何か、社会にとって価値あるものは何か。それを考えるきっかけを与えてくれるのがアートなのでは」と問いかけがあり、帆足氏が答えます。
帆足氏:一人の力で世界を変えることはできないが、アートで一人の世界を変えることはできる。この言葉を聞いて納得したのは、世界を変えようと大きく考えすぎると難しいが、誰か個人を変えようというイメージでまさにアーティストは取り組んでいるなと。だからこそ、全部は難しいが、一部分は価値が伝わり未来に残る可能性が高い
では、その価値をどうすれば伝えていくことができるか。価値を伝えたいがゆえに「アートは不要不急ではない」といういい方をする場合も多いが、それには懸念を感じると橋本氏はいいます。
橋本氏:アートに携わる側が「アートは不要不急なものではない」といえばいうほど独善的に見えてしまい、逆にアートに対して距離を感じてしまう方が増えてしまうのではないかと心配している。自分たちだけは特別だ、と独善的にも見えてしまうからだ。
むしろ国民の命は平等に大切だから、仕事を失って減収を余儀なくされている人に平等に支援すべき。アートに携わる側も、その事実を伝えるために組織だってどれくらい仕事や収入を失っているか、を伝えるべきだ。アートの世界にいる人だけで考えると周りが見えなくなる、本質が伝わらなくなる面もあるのではないか
そのような懸念に対し、帆足氏が提案するのは、アートの外にいる人の声を拾うことです。
帆足氏:アートを知り尽くしている人がそのおもしろさを知っているのはあたり前なので、アートを語っても逆に説得力がないなと。それよりも、あまりアートを知らない人が意外とおもしろいよ、と勧める方が、初めてアートに触れる人にとっては新鮮味があって興味が湧くのではないか
「なるほど。価値を適切に発信することができれば、無限大のチャンスが広がっている、そんな時代だからこそ、アートの価値をいかにして伝えていくか。これからも皆で考えていきたいと思う」という若林氏の言葉で締めくくられました。
みんなで考えるQ&Aタイム
最後に視聴者の皆さまからの質問について登壇者が回答しながら議論が進みました。いくつかご紹介します。
Q1:セクショナリズムに毒されず、「誰かの取りこぼしをひろう」スタッフを育成する効果的な方法は?
布垣氏:役割を細分化せず、必要なときにはお互いで助け合える"多能工化"が大事。トヨタ博物館ではイベント時は、いつもの役割を超えて全員参加してもらう。一人ひとりが自立的に動かざるをえない。そうした組織は変化にも強い
橋本氏:グループミーティングの司会を持ち回りでやってもらうようにしている。少しずつだが、互いの情報を自然と持ちあわせられるようになる。まずはそこからだと思う
Q2:現代アート作品を理解したいのに難しい。どうすれば?
帆足氏:美術史をひもときながら、体系的に理解するところから始めると大変なので、まずは自由に楽しんでいいと思う。一人気になる作家を見つけて、その人の人生と時代と作品をシンクロさせながら触れていくと見えるものがあるはず。現代アートは現在進行系で、アーティストが同時代を生きているのも貴重だ
Q3:アート関係者のみなさんが企業に期待することは?
若林氏:仕事上で培ったスキルや技術、あるいは情報など、企業や社員の方々の持っている専門性をいわゆるプロボノとして、ぜひ提供していただきたい
帆足氏:民間企業は営利目的で活動されているからこそ、貪欲に先端的な考えを取り入れている企業が多いと思う。そのノウハウをぜひ参考にさせていただきたい
ジャンルを越えたからこそ見えた共通の課題と未来像。これからも、それぞれの枠を越えてアートについて考えていきたい。出演者、そしてネットTAMの強い思いを一つにして、締めくくられました。
(2021年2月12日)
取材・文:日下部沙織 / 箱田高樹(カデナクリエイト)