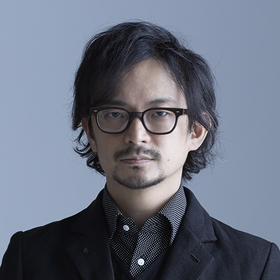時代に逆らい、未来を考える。
ライゾマティクス真鍋大度の流儀

早熟な少年時代
さまざまなメディアにご登場されていて、ご活躍ぶりが目覚ましい真鍋さんですが、そんな中で複数のインタビュー記事を拝見していると、ご両親が音楽にかかわる仕事をしていたというお話をされています。それは現在の真鍋さん、ライゾマティクスにも大きな影響を与えていると思いますか?
真鍋:そうですね。父がベーシストで、母がヤマハでシンセサイザーの開発にかかわっていたこともあり、家に音楽機材がたくさんあって。それを遊び道具にして、小学2年生くらいのころから簡単な音づくりをしていました。
それと、アメリカに住んでいたときに、Atari VCS(1977年にアメリカで発売した最初期の家庭用ゲーム機)で『フロッガー』というアクションゲームに出会って、それ以来ビデオゲームの虜になってしまって。日本に帰国した後も、習いごとの行き帰りに渋谷東急(現在のヒカリエにあった商業ビル)のゲームセンターに通ってはひたすら遊んで、そこで覚えた音を、自宅のシンセで再現して……というのが最初のクリエイティブな活動でした。ゲームそのものをつくりたいという欲望もあったから、ゲームブックを自作したり、親に買ってもらったパソコンでプログラミングしたり。それが原点と言えるかもしれないですね。今でいう音ゲーみたいなものもつくっていました。
最初の『beatmania』の稼働が97年ですから、むちゃくちゃ早い(笑)。
真鍋:小5ぐらいでしたから、たしかに早かったかも(笑)。その後、中学に入ると家でMTVを見られるようになって、洋楽、ラップを経由してアメリカのストリートカルチャーに憧れて、中3のころにはすでにクラブに通っていました。代々木のチョコレートシティとかわかりますか?
わかります! さすがに行ったことはないですけど。
真鍋:ちょうど日本語ラップの第2次ブームぐらいの時期で、EAST ENDがフロントで、前座がRhymesterという時代。そこで「DJやりたい!」なんて通ってくる中学生がいると、大人は喜んで技術を教えてくれました。それでDJにどっぷりハマって、大学のときは週6でDJみたいな感じ。広告関係のイベントの仕事をしたり、アメリカのエージェントと契約して海外アーティストのバックDJとして1万人ぐらいのお客さんの前に立ったり、ずいぶん規模のデカい現場を体験していましたね。振り返ってみると、そのときに見た風景や音圧の感覚が忘れがたくて、今もエンタメの仕事を続けているところがあると思います。

音との新たな出会い
アートとの接点を持ったきっかけは?
真鍋:東京理科大の数学科に通っていました。建築学科に000studioの松川(昌平)さんとかおもしろい人たちが大勢いて。彼らはダムタイプの池田亮司さんと組んで、展示の音楽をつくってもらったりしていましたが、あるとき、どうしても池田さんが動けないときがあって、音源を渡されてスピーカー8台を使ったサラウンド音源の音響制作を依頼されました。
DJやバンドの場合だと、出音のインパクトがすべて、というスタイルでしたが、松川さんたちは「空間自体が静まるような音楽が欲しい」とかコンセプトを重視する音楽を求めてきました。最初は「そんなの無音が一番静かに決まってんじゃん(笑)」なんて理系な発想で考えていましたが、エリック・サティやジョン・ケージの音楽を知って、人間心理を相手にする音楽のスタイルがあることに驚いて。それがきっかけですね。
IAMAS(情報科学芸術大学院大学。世界的に活躍するアーティスト、エンジニアを多数輩出している)(岐阜県)に入った後も、しばらくは池田さんのモノマネっぽいサウンド作品をつくっていました。懐かしい(笑)。
やはり音が原点にあるんですね。
真鍋:そうですね、基本的にサウンドですね。だから今も僕自身は映像表現にあまりこだわりはないです。
しかし、実質的なデビュー作といえる《Electric Stimulus to Face》(2008)は、筋電センサーを用いて顔の表情を強制的に動かす身体性の強い作品ですね。同作と音楽の間には距離を感じます。
真鍋:でも、あれもサウンドアートの延長から生まれたんですよ。スピーカーから出る音で勝負する作品は、池田さんをはじめ先達が大勢いたから。だったらスピーカー自体を考えようと思って、巨大な振動子を家に取りつけて、家自体をスピーカーにするような実験をずっとしていました。
振動子が生み出す低周波が生体に与える影響っておもしろいんですよ! たとえば瞬きが止まらなくなるとか、呼吸できなくなるとか、トイレに行きたくなるとか。それが《Electric Stimulus to Face》につながっていきました。
そして、同作がYouTubeでバズったことから、ライゾマティクスと真鍋さんの名前が世界的に知られるようになった。
真鍋:その1年前にダムタイプの藤本隆行さん、川口隆夫さんたちとつくった『true/本当のこと』(2007)での経験も大きかったです。さらにその原型となる「Tablemind」(2006)という作品では川口さんが「外からは何も動いていないように見えるけど、筋肉は活動しているダンスにしたい」とおっしゃっていたのですが、それだけだと外から見てなんの変化も感じられないですよね。そこで筋肉の収縮をセンシングして、それをトリガーにして音が鳴るようなアイデアを提案して、かたちにしました。
その後も、川口さんや白井剛くん、モノクロームサーカスとコンテンポラリーダンスの作品に多くかかわりましたが、僕が好きなビートミュージックよりも、持続的で抽象的な音楽を求められることが多くて、ちょっと違うものをやりたかった。なんだったら自分で踊ってもよかったんですけど。
真鍋さん自らですか!
真鍋:鍛えられた身体が踊る、ということがダンスの条件だとは思ってないですからね。でも当時はやっぱり自分で踊るのはちょっと恥ずかしかった(笑)。でも顔の筋肉を動かすならハードルは高くない。それが《Electric Stimulus to Face》が生まれたきっかけの一つです。音からスタートしつつ、そのコンセプトを体現するメディウムとして身体と、身体を使うダンスが適していた。それは今も続いている発想だと思います。
ライゾマティクスの独自性とは?
真鍋さんの活動の特徴として、制作プロセスやプログラムを広く公開することがあります。そういった公共性への意識はどこから生まれたものですか?
真鍋:作品として最初に意識したのは、Perfumeのダンスのモーションキャプチャーデータを2次創作のために公開した《Perfume Global Site》(2012)です。それ以前もオープンソースのツールを使って開発したり、自分の書いたソースコードを公開したりはしていましたが、そういったシェアやオープン化の発想は自分が若いころからかかわっていたインターネットコミュニティーではごく当たり前のことで、特に新しいことをしようとしたわけではないです。

+Perfume "Global Project #001”
(2012 copyright: Amuse Inc. and Rhizomatiks Co.,Ltd, Universal Music LLC,)

+Perfume "Global Project #001”
(2012 copyright: Amuse Inc. and Rhizomatiks Co.,Ltd, Universal Music LLC,)

+Perfume "Global Project #001”
(2012 copyright: Amuse Inc. and Rhizomatiks Co.,Ltd, Universal Music LLC,)
そういった比較的歴史の短い分野の気風を取り込みつつ、特定の個人の作家性に依存せず、大勢のクリエイティビティとスキルをまとめ上げながら活動するところに真鍋さんとライゾマティクスの同時代性を感じます。
真鍋:自分一人では映画やパフォーマンス作品は絶対につくれないですからね。個々が高い専門性を持ち、かつ価値観を共有できるスタッフを集められるかがライゾマティクスの活動の核だと思います。理系もいれば文系もいて、プロデュース能力の高い人もいる。そうでなければ多種多彩なプロジェクトに対応できないし、時代の趨勢である映像表現のバリエーション競争に飲み込まれてしまって、それはおもしろくない。僕らとしては、やっぱりアイデアや仕組みのおもしろさで勝負したいわけです。
そういう意味では、ライゾマティクスは現代的な制作集団だと思われがちですが、時代と逆行していると僕は思います。制作効率は高くないですし、作品のマネタイズも簡単じゃない(苦笑)。だから会社組織としてはかなり間違ってるんですよね。アメリカだとパフォーマンスの制作にしても細分化されていて、LED担当はこの会社、繊維担当はこの会社、という感じで果てしなく分業していく。でもそれだとクリエイティブの喜びを100%味わえないじゃないですか。だから僕らは最適化しないように気をつけている。
先端技術に目を向けながら、効率化からは逃げようとする、というのはユニークな立ち位置ですね。
真鍋:だから僕らは、世界的な有名企業に比べてもスピードはものすごく速いし、クオリティも高い。でもマネタイズのことだけ考えるなら、映像だけやっているのが一番よいと思います(笑)。
機動性の高さが、ライゾマティクスの先進性を担保しているということですね。しかし、後方から迫ってくるマス(大集団)に飲み込まれる恐怖もあるのではないでしょうか?
真鍋:最近は少し感じるようになりましたけど、その多くは劣化コピーという感じなので、そこまで脅威ではないですね。実際、室内でダンサーとドローンが一緒にショーをやるというのは、おそらく僕らだけでしょうし。あと、機動性の高さという話でいうと、オリンピックの仕事を受けると同時に、「America’s Got Talent」にエントリーしちゃったりするのはライゾマらしさといえるかも(笑)。
アメリカで人気の、公開オーディション番組ですね。知られざる才能が登場する登竜門的な番組ですが、そこにライゾマティクスとしてエントリーした?
真鍋:そうなんですよ。あと2回勝ったら賞金1億円だったけど、リオの本番 とかぶってしまって惜しいことに辞退しちゃった。
クライアントからの仕事を受けつつ、非営利の作品制作も同時に進めていくのがライゾマティクスのおもしろいところですよね。依頼がなくても、独自に実験を重ねている。
真鍋:アートプロジェクトのよいところは、具体的な成果を得られなくても、あるいはつくっているうちに全然違うものになったとしてもOKというところです。メーカーでいうところの研究開発みたいな感じですね。研究開発だけではなくて、作品として強度がちゃんと出るかどうかも実験する。ゴールやハードルを自分たちで設定できる自由さを手放したくありません。自分以外の人が最終的なジャッジ権を持つクライアントワークでは100%の自由はありえませんから。アートとエンターテインメントは、僕の中ではかなり明確な区別があります。
歴史を学び、伝えていく
そういった中で、リオ2016オリンピック競技大会閉会式東京2020フラッグハンドオーバーセレモニーはライゾマティクスにとってもかなり異色な仕事だったのではないでしょうか? ライブやCMであれば限られたファンやクライアントのニーズを考えればよいですが、世界的な催事であるオリンピックでは国家や民族という、とてつもなく広い概念を代替しなければいけない。
真鍋:映像ではなくパフォーマンスでメッセージを伝えるというのは、かなり抽象化した表現なので難しかったですね。日本側が伝えたいキャッチコピーは明確にあるけれど、言語は使えない。そこで僕らが担ったのは、言語を抽象的で非言語的なものに変換する作業でした。その制作過程の現場では「これだと伝わらない」「でも、ここまで説明的なものにしてしまったらカッコ悪いよね」というやりとりが繰り返されました。普段のプロジェクトよりもかかわる人数が多く、意思決定も大変でしたね。
技術的なハードルはいかがでしたか?
真鍋:実はそこはある程度見通しがありました。というのも、僕らはこれまでにアリーナやスタジアムでの作品展開の経験を重ねていて、起こりうるトラブルやその回避方法もきちんと経験として蓄積されていたから。それはクリエイティブというより、エンジニアリングの問題で、いかにリスクを事前に取り除くことができるか、という勝負です。それがきっちりできる集団というのは、世界的に見ても多くなく、そこにライゾマティクスが対応できたという事実は代え難い収穫です。
一方でフラストレーションを感じるのは、オリンピックの運営上、今までのように制作のノウハウを公開できないことですね。これまで僕らがしてきたように情報を公開できれば、無用なトラブルやアクシデントを回避するための経験を業界全体で共有できるわけですから。それが僕らの意思とは別に、独占状態になってしまうのは本意ではありません。オリンピックが持つ特殊な体制が、クリエイティブを推し進めると同時に、少し窮屈にもしている。それは、今後変わっていってほしい点ですね。
今後の展望ということでいうと、真鍋さんは2020年、オリンピック以降にクリエイティブシーンはどのように変化していくと思いますか?
真鍋:正直、あまり未来のことを考えないんですよ(笑)。でも、今いったように、研究開発や制作の蓄積が秘匿されて、それ以降応用することができなくなる環境は変わってほしいし、変えていきたいです。
言い換えると、それは芸術表現における技術史のアーカイブ化、歴史化ということなのかなと思います。月刊誌『美術手帖』でのライゾマティクス特集で特に印象的だったのが、真鍋さんが歴史を継承して、次につなげていくことにとても意識的であることです。
真鍋:自分自身の活動のためにも、歴史を俯瞰して見られる状態を常につくっておくことは意味がありますからね。あとは単純に、歴史を調べるのはヒップホップの元ネタ探しみたいな感じもあっておもしろいです(笑)。たとえば、リオ五輪では矩形の造形物を使ってさまざまなエフェクトを生じさせるという演出を行いましたが、歴史を遡れば、バウハウスや、サーカスのジャグリングにも同様の技術はありました。では、今回のパフォーマンスにおいて僕らの独自性がどこにあったかというと、可視化されない仮想世界のオブジェクトを現実世界に引き出すためのインターフェースとしてフレームをつくり、振り付けを加えているという点です。そうやって歴史を詳細に検証することで、既存の表現形式を時代に合わせてアップデートさせることができる。それは歴史的存在としてのアーティストの大きな役割だと思います。
それと同時に、技術や思想を後の世代に伝えていく活動も真鍋さんは積極的に行っていますね。中学生を対象とするワークショップなどはその好例です。
真鍋:Perfumeの仕事にかかわるようになってから、中学生や高校生からメールが殺到するようになりました。たとえば「年賀状のQRコードに、カメラをかざすとPerfumeが踊るようなのをつくりたいんですけど」とか。結構おもしろいアイデアだし、なによりカワイイじゃないですか。
中学生の熱いファン心理がいいですね(笑)。
真鍋:それに応用可能なソースコードもネット上には公開されていたので、メールで教えてあげたりしていました。実際、そうやってやりとりしていた中学生が今や慶応SFCに入学して、けっこう優秀な活動をしていたりするんですよね。

photo by Muryo Homma(Rhizomatiks Research)

photo by Muryo Homma(Rhizomatiks Research)
師弟関係ですね(笑)。
真鍋:でも直伝だけだと効率が悪いので、そこで見どころのありそうな子たちを選んでワークショップを行っています。その子たちがさらに技術を広めてくれればいいな、と思って。個人的な活動から始まった取り組みですが、おもしろがってくれる人がけっこういて、番組で取り上げたりして。今後は、もうちょっと広くに共有できる枠組みを展開していきたいと思っています。
自分の原点はいろいろありますが、数学のおもしろさに早いうちに目覚めたことはとても大きかった。だから、数学に苦手意識を持ってしまう前の、中学生や高校生の時期にいろんな経験をしてもらいたい。そして自分たちで何かをつくってほしい。そういう願いもワークショップの活動にはありますね。

取材概要
- 取材日:2017年2月24日
- 取材地:株式会社ライゾマティクス
- 取材先:株式会社ライゾマティクス 取締役 真鍋大度
- 取材・構成:島貫泰介
- 取材者:島貫泰介、ネットTAM運営事務局(トヨタ自動車株式会社 内田京子、公益社団法人企業メセナ協議会 佐藤華名子、入江拓也)