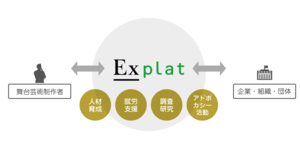「デザイン × エンジニアリング」
異なる分野をつなぐ手法と発想
近年、地域密着型のアートプロジェクトが全国各地で数多く実施されるなど、アートが社会に出ていく機会が増えています。ますます多様化していく社会のあり方に呼応するように、アートと社会をつなぐアートマネジメントも多種多様になり、アートの世界だけではなく、つながる先のことをよく知ることや状況に対応していくことが、いまアートマネージャーに求められています。
今回取材に伺った「takram design engineering」は、エンジニアおよびデザイナーとしてのバックグラウンドを持ち、両分野を掛け合わせたものづくりをされると同時に、自らが架け橋となって異なる業種や人をつなぎ、その独特な発想のもとに全員参加型プロジェクトを体現しているような企業です。異分野のつなぎ手としても注目されているtakram design engineeringさんの思想やものづくりの姿勢、そしてこれまで生み出してこられた数多くの手法に着目し、社会とアートをつなぐアートマネージャーへのヒントとして具体的なお話を伺いました。
芸術環境KAIZENファイルに寄せて
渡邉:あらゆる成熟産業が内向きになりがちなベクトルを持っているときに、そのベクトルを外にも開いていこうという試みがあるとしたら、多分それはいろいろなところで起こっていて、アート以外のさまざまな分野でも起こっているはずです。例えば我々はものづくりを生業としているメーカー企業の方々と一緒に製品を開発することが多いのですが、そういうなかではジャンルを超えたコラボレーションが、求められています。このような問題意識を含みつつ、さらに深めながら、それに留まらないお話ができるのではないかと思っています。
design engineering(デザインエンジニアリング)とは?
始めに、「takram design engineering」(以下「takram」)について、どのような事業をなさっている企業なのでしょうか。
渡邉:takramのメンバーの多くは、工学的なスキルをベースに持ち、なおかつデザインのスキルを習得した「デザインエンジニア」です。デザインとエンジニアリングを融合させたものづくりをしたいと考えている仲間が集まっています。1つのジャンルにとらわれず、複数の領域を混ぜ合わせて初めて生まれる価値に注目し、分業化されてしまいがちな複数の職能をクラフツマンシップ的に1つのものに戻していくような "ものづくり"をしている企業です。「デザインエンジニアリング」とは、「デザイン+エンジニアリング」ではなく「デザイン×エンジニアリング」をめざす手段や考え方で、デザインとエンジニアリングをブリッジしたり、より高いレベルで統合していきます。どちらの言語も使えるからこそ発想できるものや、推進できるプロジェクトが必ずあると考えています。
実は、デザインとエンジニアリングを掛け合わせるという考え方は様々なメーカー企業とお仕事をご一緒するなかで必要に迫られて生まれ、強化されてきたものです。企業のものづくりの現場で「コンセプト」に関連して多く見られる失敗には2種類あります。最初に決めたコンセプトがかえって足枷になってしまい、事後的な臨機応変な対応が難しくなる場合と、もう1つはコンセプトや企画が曖昧なままものができ上がってしまい、コンセプトを後付けしてしまう場合です。また、日本の大きな組織にありがちなのが、メンバー全員に「よい製品をつくろう」という共通の目的があるはずなのに、それぞれが追い求める目的が少しずつ異なっているため、部署間で微妙な対立構造が生まれるケースです。商品企画、マーケティング、広報、経営戦略、デザイン、エンジニアリングなど、それぞれの部署間で横の壁が存在します。このすべての横の壁を通っていくうちに、最初は星のように輝いていた企画の角が削れて普通の丸のようになってしまう、それを上層部にプレゼンしても当然「特徴がない」などNOと言われて戻されてしまいます。いわば、横の壁が民主主義的すぎて、縦の壁が権威主義的すぎるのです。全体を俯瞰できる職種や職能がないと、各部署がそれぞれの目的を全うしようとするあまり、星の角をそぎ落とすことになるんですね。日本の企業のものづくりは折衷案が多いと言われるゆえんです。
では、プロダクトに関わる全員の考えやスキルがフラットな場で、一緒に「考えながらものをつくり、つくりながら考える」という、手と頭の動きがフィードバックされて循環していく本来のものづくりの姿を取り戻すにはどうしたら良いか。この課題を解決するための手法が、"プロトタイピング"と、"ストーリー・ウィーヴィング"です。

Planning, Opration & Creative Direction: Kotaro Watanabe, Kinya Tagawa
Production: Diamond Design Management Network
photo: Takashi Mochizuki
© 2012 takram design engineering
© 2012 Diamond Design Management Network
takramの手法
"プロトタイピング"と"ストーリー・ウィーヴィング"とは、具体的にどういったものでしょうか。
渡邉:プロトタイピングとは、それ自体は「試作品をつくること」を意味します。ただ、我々は単に試作を作るだけでなく意識的に、デザイン、エンジニアリング、商品企画、マーケティング、ときには経営といったあらゆる人を集め、1つの試作品を前にして議論することを行います。実際に触れられるものが目の前にあることで、それぞれが高い専門性を持ちながらも1ユーザー、1消費者としてのコメントができるようになります。企画書レベルではポジショントークになりがちな会議を、まったく私的なものに変えてしまう、これがプロトタイプの力です。例えば、普段は工数増加を望まないエンジニアリングの代表者が「もっとこうした方が良い」と自ら仕様変更を提案するという、普段は絶対に起こらない出来事が、プロトタイプを前にすると起こったりもします。ですが、どうしても越えられない壁がありました。それぞれの立場の人たちが互いに理解し合うための共通言語を得られない、という問題です。これはプロトタイプだけでは到達し得ない地点でした。そこで登場したのがストーリー・ウィーヴィング(以下「SW」)という考え方です。
SWは"もの"を計るための「物差し」と言えます。先ほどのポジショントークと同じように、"もの"に対してデザイナーは「デザインのうえでは良い」と言い、エンジニアは「エンジニアリングのうえでは良い」という言い方をします。つまり、自らのポジションの外では、何を基準に判断すれば良いのかがはっきりしないのです。そんなとき、"もの"の背景に「この社会情勢でこの人たちにこういうものが求められている」という具体的なストーリーがあると、プロジェクトは誰もが理解できるような力強さを持ちます。このストーリーは最初に誰かがつくるようなものではなく、製品開発プロセスの中で日々更新されて良いものです。後付けでも継ぎ接ぎでもない、あるべくしてあるものなのです。「ウィーヴィング」は「編み上げる」という意味です。縦糸にものづくりを、横糸にものがたりを置き、可逆的段階的プロセスの中で逐一全員参加の物語を編み上げていくのがSWです。これによって、大きな企業や大勢の人が関わる場合でも、全員が一緒に行う、本来あるべき"ものづくり"の姿に近づきます。これがプロトタイピングとSWの組み合わせです。「ものづくりとものがたりの相互作用」と我々は呼んでいて、実現したときにイノベーションに最も近づくと考えています。

Planning, Opration & Creative Direction: Kotaro Watanabe, Kinya Tagawa
Production: Diamond Design Management Network
photo: Takashi Mochizuki
© 2012 takram design engineering
© 2012 Diamond Design Management Network
渡邉:実はSWは個人の問題、メッセージの伝え方にも当てはまります。例えばデザイナーやエンジニアは、自分のスキルに注力するあまり、プレゼンテーションやコミュニケーションに注意を払わず、せっかく良いものを持っていても組織のなかでうまく伝えられない人が多いんです。これはあらゆる人に言えることですが、プレゼンターは、つくりあげた「もの」について、状況に応じて異なる方法で語る術を持たなければならないと思います。誰に語りかけるかによって、ストーリーの強調すべき箇所も変わってきてしかるべきです。ものづくりとものがたりを寄り添わせるSWという手法は、そうしたスキルを養うためにも、必要とされているのかもしれません。
ものづくりとものがたりが編み上げられてひとつのかたちをつくる、という流れが本来的なものづくりに近く、かつさまざまな場面に当てはまる手法であるというのは、分業化に慣れた社会においては興味深い現象ですね。他にも手法はあるのでしょうか。
渡邉:よく使う手法に「プロブレムリフレーミング」というものがあります。問題をリフレーミングする、つまり置き換える、問題の枠組みをずらしてしまう、ということです。ドイツのカッセル・ドクメンタという現代アートの祭典で、100年後の水筒をデザインしたことがありました。100年後というと、人間の価値観が大きく変わっているはずですから、つまりは「新しい価値観に沿った水筒をデザインしてください」というオファーです。まず100年後の世界を想像するところから始まります。人口が激減して地球の汚染が進んでいて、もしかしたら放射性物質があって、残された陸地は海面上昇で境がなくなり、人間がつくってきたあらゆるインフラや街、物や食べ物などが大幅に失われてしまっている状態かもしれない。そんな極限の状態に住んでいる人間が持ち歩いている水筒...。いろいろな水筒を考えました。植物の中に水分を蓄えようとか、杖の中にフィルターをつくって、トレッキングして歩くときに自動的に地面の水分が底面の接地部から吸収されて、フィルタリングされた水が持ち手の箇所から飲める、とか。ところが、ディレクターには全部だめと言われてしまいました。そこで、ボトルをデザインすることを一度やめて、人間と水との付き合いを根本から考え直してみることにしました。調べてみると、成人男性は、尿・大便・呼気・汗、の4つの経路から1日に2.5リットルの水を失うそうです。では、この4つの経路から失われる水分を少なくできたら、そもそも今と同じ分量の水を飲まなくても良いのではないかと考え、体の中に埋め込む水の浄化リサイクルシステムとしての人工臓器群をデザインしました。「水筒をつくれるか」という問いに対して、「人工臓器を提案する」、これがプロブレムリフレーミングです。問題をどこに置くか、ということ自体を問い直せるのは、デザインがもたらす力の1つかもしれません。

右:Artwork by Bryan Christie, with organ rendering by takram design engineering
Kinya Tagawa, Project Leader (from 10/2011)
Kotaro Watanabe, Story-Weaver (from 10/2011)
Kaz Yoneda, Lead Designer (from 10/2011)
with Moon Kyungwon and Jeon Joonho, Artists
Original concept development by Motohide Hatanaka, Ph.D., Project Leader (until 10/2011)
(ex-takram)
Photographs by Naohiro Tsukada
Figure Artwork by Bryan Christie (with the addition of organ rendering by takram design engineering) © 2012 takram design engineering
枠組みそのものを問い直して新しい価値を持つものを生み出すという視点は、アートにも通じるものがあると思います。「100年後の水筒」はまさに現代アートの展覧会でのお話でしたが、アートとデザインについてどうお考えですか?
渡邉:我々がものをつくるとき、アートとデザインを特に分けて考えていません。ものがたりを編みながら試作をたくさんつくって、そのなかで自分たちで考え、考えながらつくるというプロセスはどちらも同じだと思っています。もちろん、異なる見解もあります。例えばRISD学長のジョン・マエダさんは、アートとデザインを全く違うものととらえていて、デザインは解決策を提供しアートは問いを提供する、と仰っています。これを僕なりに言い換えるならば、アートはどちらかというと、それこそ哲学や考え方を示すもので、人間が進むべき方向性を指し示すコンパスのようなものです。一方で、目的地もしくは方向があるときに、どうやって向かっていくかという具体的な手段がデザインです。このように考えると、デザインは必ず想定されたユーザーないしターゲットがいるんですよね。「これは歩ける人に使ってもらう靴です」「これは車が運転できる人のための手袋です」「目が見えない人が使える杖です」と。
また、MOTのチーフキュレーターの長谷川祐子さんが書かれた本の中に、『なぜ?という問いが人間を深く美しくしてきた。なぜ生きるか? を問う生き物は人間だけである。なぜ生きるか? という問いに対して人が最初に見出した答えは神。次に見出した答えは科学である。アインシュタインが物理を、ワトソンとクイックが生命を解き明かした今、残る問い、なぜ? は思考や意識といった人間の脳の中の問題である。人間が生み出した2番目の答えである科学が扱う命題は、人間の中にある考え方の問題であり、その意味において、科学の命題はアートと哲学と不可分ではないか』という記述があって、ジョン・マエダさんの「アートは哲学や考え方を示すものだ」という考えと一致するなと思いました。Whyを提供するものがアートだとしたら、デザインはそれに対するHowやWhatという、具体的な手段の形を提案するものです。
ただ、現代的なデザインとアートは徐々に接近している流れもあると思います。そもそもジャンルを分けることの意味が薄れてきているのが現在でしょう。人工臓器を出展したのは現代アートの文脈でしたしね。アートかデザインか、ということを僕たち自身があえて明言しなくても、見る人や場面、文脈が決めてくれれば良いのかなと思っています。
異なるものをつなぐブリッジの行く末
ジャンルとして分けられている領域が薄れつつあるということでしたが、その流れは今後どのようになっていくとお考えですか?
渡邉:僕が監修と解説文執筆をさせていただいたビジネスモデルの設計書『THIS IS SERVICE DESIGN THINKING. Basics - Tools - Cases 領域横断的アプローチによるビジネスモデルの設計』に、「領域を何か特定してしまっては、もう現代的な競争には勝ち残れない」という含意があります。iPhoneやNike + FUELBANDなどにも見られる、サービスデザイン思考の考え方自体は前からありました。でも、ものづくりもソフトウェアもインターフェースもサービスもネットワークも全部渾然一体となって体験として提供されていて、従来型のデザイナーやエンジニアという職種1つでは語り得ないレベルにまで統合されてきたのは、ここ数年のことでしょう。そのレベルのものをつくるには、サービスデザイン思考の分野横断、領域横断のアプローチが求められています。いまや「自分の領域はプロダクトデザインだからそのことしかやりません」では通用しません。何かに特化したプロフェッショナルはいつの時代も必要ですが、体験価値を提供する立場にある人物が1つの専門性への特化に拘りすぎると、現代の開発スピードに置いていかれてしまいます。1つのものをつくっている間に世界では別の人たちがもっと速くつくってしまうので、分野を横断して同時にいろいろなことを考えられるようにならなければ競争には勝てません。こういうことが世界的なトレンドになっています。ですから、分野を明確に分けること自体がもうあまり必要ではない時代になっているかもしれない、ということを感じています。

境界が希薄になることがさらに加速する、その過程で領域横断的な考え方が必要になるからこそ、takramさんのような存在が注目されているのですね。異なる領域の方々と仕事をするために渡邉さんが大切にしていること、心がけていることはなんですか?
渡邉:我々の仕事は、他分野のいろいろな人たちと話すことで成り立っていますから、純粋に対話、聞くこと・話すことしかないと思っています。例えば、伊藤忠のグループ会社で、マーケティングやブランディングを専門としている伊藤忠ファッションシステムという会社が立ち上げた「ifs未来研究所」では、経営とクリエイティビティを重ね合わせています。僕は外部研究員として参加していますが、経営のグループで固まりがちな経営側の人たちと、クリエイティビティに注力してコミュニティからなかなか外に出ていかない人たちを、いかにつなぎ合わせるか、ということが研究所の取り組むミッションの1つです。この未来研究所のおもしろいところは、所長以外のメンバーがほぼ全員、外部研究員で構成されている点です。デザインエンジニア、プロダクトデザイナー、ファッションデザイナー、ビジュアルデザイナー、ITジャーナリスト、経営コンサルタント、そして建築家です。伊藤忠ファッションシステムと一見関係ないような人たちが集まって、未来研究所を動かしているんです。「他分野の人たちと実際にものをつくったり何か提言する」ことによって未来をつくっていきたいというモチベーションが、この構成から見てとれますよね。ここが、他の研究所と異なる点です。
もうひとつの事例は、「コレクティブ・ダイアログ」というAXIS、takram、IDEOの3社によるの3社によるイベントシリーズです。「デザインの考え方や手法は社会問題を解決するポテンシャルを持っている」という信念から、職業も年齢もさまざまな人たちが集まり、デザインメソドロジーを使って社会課題の解決策を考えるイベントです。グループに分かれてワークショップ形式で対話を重ねていくのですが、お互いの違いを尊重しながら質問し合い、意見を伝え合う、とても良い場になっているんです。ここで対話のきっかけとなっている手法にはSWも含まれたりしていて、これは非常におもしろいですね。
ものづくりのための「対話」と「発想」
異なる分野や領域の方々と一緒に仕事をするうえで大事な「対話」を促すには、どのような方法があるのでしょうか?
渡邉:「思っているけどなかなか言えない」もしくは「言う場がないから言えない」という場合は、「コレクティブ・ダイアログ」のように議論のプラットフォームをつくってあげることで、違いや意見を認め合い、対話がしやすくなるかもしれません。ですが、「そもそも違いを抱えていることに気づいていないから言おうとすら思わない」という場合は難しいですね。そこをどうやって言えるようにするか、と常々考えているのですが、実はSWを構成する1つの技術にその手法があります。製品開発の初期の場面でよく使う「タンジェント・スカルプチャー」という手法で、デザイン対象の名前を言わずしてそれについて語る、というものです。
例えば「コップ」というオブジェクトがあったとき、「コップ」という言葉を一切使わずにコップを表現してみるんです。「それは底面を持つが上面を持たない1つの円筒状のものである。それは一定量の水を拡散させることなく地球の重力圏内に保持できる静物である。それはテーブルの上に置かれ、人の手につかまれ、ときに合図の作法として使われ、音楽の一要素になり...」と、物理的、科学的、文化的、民俗史学的にさまざまな角度からコップを切り取ることで、コップに対する我々の思い込みと想像力の限界を共有し、「そもそも違いを抱えていることに気づいていない」状態から「こんなに多くのとらえ方があるんだ」と、違いがあることを言語によって顕在化させるのです。いわば、「コップ」と言った瞬間に陥る思考停止から逃れる取り組みですね。なお、このコップの例は谷川俊太郎さんの散文詩「コップへの不可能な接近」から来ています。
「タンジェント」は接線、「スカルプチャー」は彫刻ですから、接線による彫刻という意味です。ある点には接しているけれどそれ単体ではまだ「コップ」ではない線、つまり、「それはテーブルの上に置かれるもの」といった対象の特徴を示す1つひとつの接線をできるだけたくさん密に引いていくと、接線によって彫刻されてある像が浮かび上がります。こうして、対象そのものではなく周囲の情報から対象にアプローチしていくと、当然だと思っているからこそ言語化しないことが世の中には多く、そのために誤解が広がってしまう場合があることに気がつきます。「タンジェント・スカルプチャー」は多くの人たちと1つのものをつくったり議論したりすることを箱庭的に体感してもらう仕掛けのようなものですが、この手法を通して想像力を限界まで広げることができるかもしれないし、より文脈を含んだものを得ることで、ものがたりを編む道に近づけるのではないかと思っています。
takramのこれから
最後の質問になりますが、これからどういったことに取り組んでいきたいとお考えですか?今後の展望をお聞かせください。
渡邉:企業の戦略立案・ブランディングから具体的なものづくりまで一貫してやっていきたいと思います。企業理念についてインタビューするところから、実際にそれを哲学に落とし込み、ロゴデザインに落とし込み、それを名刺にして哲学をそのまま援用する形でプロダクトデザインに落とし込むというような、上流から下流までを全てやりたいです。表面的なスタイリングではなく、ものがたりを編みながらものづくりにつなげ、今度はもの自体がものがたりを更新して新たなものづくりにつながっていく。これはまさにSWの営みそのものです。今後もそういうふうに進んでいきたいなと思っています。ただ、我々の方法論として1つの手法にとらわれることはなるべくしたくありません。変化・成長し続けることが我々の存在意義ですから、他の手法を取り入れて、自分たちの輪郭を広げていきたいですね。常に変わっていって、常に新しいものをつくっていきたい。これが我々のアイデンティティです。
盛りだくさんのお話で、いろいろなヒントや気づきをいただきました。ありがとうございました。

Photo by Daichi Ano
Kaz Yoneda, Project Leader and Architectural Designer
Kinya Tagawa, Advisor
Kotaro Watanabe, Advisor
in collaboration with Akio Takatsuka, architecture atelier akio takatsuka assisted by Takeo Minato, collaborator, takram design engineering
渡邉康太郎プロフィール
takram design engineering のディレクター/デザインエンジニア。慶應義塾大学SFC卒業。
アテネ、香港、東京で育つ。大学在学中の起業、ブリュッセルへの国費留学等を経て、2007年よりtakram参加。最新デジタル機器のUI設計から、国内外の美術館でのインタラクティブ・インスタレーション展示、企業のブランディングやクリエイティブ・ディレクションまで幅広く手がける。代表作に、東芝・ミラノサローネ展示「OVERTURE」、NTTドコモ「iコンシェル」のUIデザイン、虎屋と製作した未来の和菓子「ひとひ」など。
多くのプロジェクトを元に体系化した「ものづくりとものがたりの両立」という独自の理論を用い、レクチャーシリーズやワークショップを企画・運営。国外の大学やビジネススクールでの講義・講演、企業向けの人事研修も多数。香港デザインセンターIDK客員講師。独red dot award 2009等受賞多数。
2013年よりAXIS、IDEO Tokyoとともに、デザイン思考を広める一般向けの連続イベント「Collective Dialogue - 社会の課題にデザインの力を」を共同主宰。著書に「ストーリー・ウィーヴィング」(ダイヤモンド社)。その他「THIS IS SERVICE DESIGN THINKING. Basics - Tools - Cases 領域横断的アプローチによるビジネスモデルの設計」(BNN新社)の監修・解説を担当。