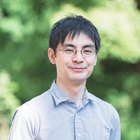第3コーナー|マネジメントサイクルを超えて
どうも。おひさしぶりです。8カ月ぶり、「はじめに」以来の登場です。本連載7本目の記事となります。みなさん、「ことば」は身体に馴染んできたでしょうか? 残りの記事は今回を含めて、あと2本です。ここまでつないだバトンを落とさぬように気を引き締めて参ります。まずは「今月のことば」から。
今月のことば
第3コーナープロジェクトの運営を競技場のトラック1周にたとえるならば、準備から実施までが、ちょうどトラック半周の第2コーナーといえるだろう。そして、第3コーナー以降は、記録や調査をもとに活動を振り返り、その成果を関係者へ報告し、検証・評価する段階である。プロジェクトを持続的に展開するためには、この第3コーナー以降が重要だ。
『ことば本』、68頁
「東京アートポイント計画」と双子のプログラム「Tokyo Art Research Lab(以下、TARL)」では『アートプロジェクトの運営ガイドライン(運用版)』の示した「ブレインストーミング→企画・準備・実施→報告・検証・評価」という円で描かれたマネジメントサイクルに沿ったプログラム展開をしてきました。この話は「はじめに」でも少し触れました。

このマネジメントサイクルの後半にあたる「報告・検証・評価」がアートプロジェクトの現場では手が回っていないのではないか。そもそも「報告・検証・評価」を行うためには、その材料となる「記録・アーカイブ」や「調査」が必要なのではないか。こうした問題意識から、TARLが重点的に取り組むべき領域を指し示すものとして「第3コーナー」という「ことば」は生まれました(厳密に考えると検証・評価は「第4コーナー」になるので「第3コーナー以降」といういい方が正しいかもしれませんが、本稿では「第3コーナー」で統一します)。
今回は「第3コーナー」に関するTARLでの議論と実践の成果をいくつか紹介したいと思います。結論を先取りすれば、マネジメントサイクルをベースに現場に欠けているパートを可視化するために生まれた「第3コーナー」という言葉を手掛かりに実践を始めてみると、どれもがマネジメントサイクルという単線の円の動きから逸脱する成果を生むことがわかってきました。アーカイブ作業に着手することはプロジェクト運営の「後半」に留まる作業ではなく、その根幹に触れるものであるということ。記録や調査を「する」ことは、それ自体がプロジェクトにかかわる人々を触発する行為になるということ。この2つの事例をご紹介したいと思います。
地盤を固める|『アート・アーカイブ・キット』と『アート・アーカイブの便利帖』
アーカイブに取り組みたいけれど、何から始めていいのかわからない。そうした悩みを解決するためにTARLでは、ふたつのツールを制作しました。『アート・アーカイブ・キット』(以下、『アーカイブ・キット』)と『アート・アーカイブの便利帖』(以下、『便利帖』)です。どちらもウェブサイトでダウンロードが可能です。全体の作業フローや各プロセスでの具体的な手の動かし方など細かいところはそちらをご覧いただくとして、ここでは要点のみご紹介します。アーカイブは、はじめが肝心! という点です。
![『アート・アーカイブ・キット』(東京文化発信プロジェクト室、2014年)。上段左から「マニュアル・シート」、「ワークフロー1<準備編>」、「ワークフロー2<実践編>[紙資料]」、「ワークフロー2<実践編>[デジタル資料]、下段左から各シートを収納するフォルダ、「進行表」(プロジェクトの進行過程で発生する資料を確認するシート)、「業務分類表」(プロジェクトで発生する資料の分類を一覧にしたシート)。Tokyo Art Research LabとNPO法人アート&ソサイエティ研究センターのウェブサイトでデータ一式をダウンロード可能。](/data/course/assets_c/2018/02/kotobabon-7-kit-thumb-1280xauto-2514.jpg)

『アーカイブ・キット』と『便利帖』は共通して、アーカイブ作業を始める前の「準備」から説明が始まっています。整理したい、もしくは整理していこうとする記録に触れる前に、記録を作成する自分たちについて確認することを大事な作業と位置づけています。たとえば『アーカイブ・キット』の「ワークフロー1<準備編>」には次の3つのステップを示しています。
STEP1|プロジェクトにかかわるステークホルダーを把握しましょう
プロジェクトが「どこで」作成されるか確認する
自分たちの組織をプロジェクトの中心に据えて、ステークホルダー(関係者や団体)との関係図をつくってみましょう
↓
STEP2|自分たちの組織の構成を把握しましょう
プロジェクトの資料を「だれが」作成するのか確認する
組織内の担当を整理して組織図をつくってみましょう
↓
STEP3|運営プロセスに沿って作成される資料を把握しましょう
プロジェクトの資料が「いつ」作成されるかを確認する
アート・プロジェクトの運営プロセスを確認しましょう「ワークフロー1<準備編>」『アーカイブ・キット』より抜粋
記録が「どこで」、「だれが」、「いつ」発生するかの全体像をイメージしておく。『便利帖』では、これに加えて「なに」が自分たちにとって大事な記録(=バイタル・レコード)なのかを確認することを準備作業に挙げています。この作業をしておくことで、それから続く、記録の作成→整理・保管→共有という一連の流れをスムーズに進めることができます。
こうした準備作業を「スタッフ全員」(『アーカイブ・キット』)、「みんなでやる」(『便利帖』)ことが、とても重要になります。つまり、アーカイブ作業に着手することは、自分たちの活動や組織の全体像に対する共通理解をつくることから始まります。
わたしたちの活動は、どのような人々とかかわり、どういう時間軸で動いているか? いったい、どのような価値を大事にしようとしているのか? こうした問いかけから議論を重ねることは、自分たちの活動の基盤を鍛え、対外的に活動を発信する力を養うことにもなるでしょう。アーカイブを始めることは、プロジェクトの「残したもの」を拾う作業だけではなく、プロジェクトを担う「わたしたち」の内側と外側の関係を縫い合わせる糸口を見出す作業でもあるのだと思います(こうした関係をつなぐ作法については前回の「ブツ切れにしない|広報コミュニケーション活動、3つの視点」にも詳しく書かれています)。

プロジェクトを触発する|記録と調査のプロジェクト「船は種」
マネジメントサイクルの行き着く先は「検証・評価」です。活動の成果を振り返ることで次の企画の改善につなげる、関係者への説明を行う、社会に新たな価値を発信する。検証と評価の使い道はさまざまです。ここで注意すべきは、こうした成果の確認には、それ相応の記録や調査が必要だということです。そして、評価や検証の材料を現場と同時進行で行うことは可能だろうか。この問いに向き合うため、TARLでは進行形のプロジェクトに併走する「記録と調査のプロジェクト」を試みました。
プロジェクトは舞鶴で続いてきた「種は船 in/from 舞鶴」(2010年~2012年/主催:一般社団法人torindo、以下、「種は船」)の3年目の現場と連携し、大阪を中心に活動を展開するNPO recip(特定非営利活動法人地域文化に関する情報とプロジェクト)とNPO remo(特定非営利活動法人記録と表現とメディアのための組織)の混成チームによる記録と調査のプロジェクト「船は種」(以下、「船は種」)を実施するというものでした。
プロジェクトの詳細はTARLで発行した、いくつかのドキュメント(記録!)に残していますので、関心ある方はそちらにアクセスしてみてください*1。ここでは(またしても)要点のみをお伝えします。「船は種」が掲げた「アートプロジェクトの当事者の手によってさまざまな関係性や歴史、人々の記憶を前景化させるということ」というテーマと、それが「種は船」の現場に何を引き起こしたのか、という点です。
*1:「仕事を知る1」『Tokyo Art Research Lab 思考と技術と対話の学校 基礎プログラム1[思考編]・2[技術編]「仕事を知る」講義録 2015』(2016年、102-109頁)、「Topic3 記録・調査の体制づくり:チームという戦略、現場との距離」『アートプロジェクトのつかまえかた:「評価」のためのリサーチの設計と実践』(2013年、46-59頁)、『記録と調査のプロジェクト『船は種』に関する活動記録と検証報告』(2013年)。いずれもTARLの一環で発行。
アートプロジェクトのプロセスにはアーティストや事務局スタッフ以外にも地域住民などさまざまなかかわりをもった人々が参加します。そうした人々はプロジェクトの単なるお手伝いではなく、主体的な担い手として、ともに手を携えて現場を動かします。その様子は本連載の第4回「アーティスト、ボランティア/サポーター|アートプロジェクトを「ともに」動かす」でも触れました。
しかし、プロジェクトが終わり、成果を広く共有しようとするとき(「報告・検証・評価」の段階ですね)、どうしてもアーティストやディレクターなど名前の立つ人々を主語に語ってしまいがちです。すべてが、そう狙ったからではなく、意義を語るための材料が残されていないことにも由来するのだと思います。こうした課題に「船は種」は「当事者」自らの手を動かし、関係した人々の「記憶を前景化」させ、記録に残すことを試みました。
「船は種」の軸となったのは「フネタネスコープ」という映像記録手法と「フネタネのつどい」という「フネタネスコープ」の記録を活用した記憶を触発する語りの場づくりでした。

また「フネタネのつどい」だけではカバーし切れない人々の声を拾うためにアンケートやインタビューも行われました。「船は種」の報告書は、大きさA4、厚み1.5cm、重さ750g、約290頁。この重量感あふれる報告書には延べ27人に約21時間をかけた約22万5000字のインタビューテキストが収録されています。
「船は種」のディレクターを務めた吉澤弥生さんはご自身の著書のなかでアートプロジェクトの成果として、そこに「参加した人がその体験を日常生活に生かす方法や、その人がのちに別プロジェクトに参加したり自身で何かを企画したりするといった『飛び火効果』」を挙げています*2。この報告書に収録された「厚み」のある語りの数々に触れていくと「種は船」というプロジェクトにかかわった人々の日常生活に「種は船」の経験が浸透している姿が浮かび上がってきます。
*2:吉澤弥生『芸術は社会を変えるか?─文化生産の社会学からの接近』青弓社、2011年、73頁。
当然のことですが、こうした記録や調査の活動を行うことは、「船は種」のプロジェクトメンバーが実際に舞鶴を訪れ、「種は船」の活動を行う人々との接点をとり、関係をつくることも意味します。「種は船」の現場が動くのと併走して記録をとる。インタビューで深く話をきく。「フネタネスコープ」の手法を伝え、「フネタネのつどい」の場を回す。こうした一連の「行為」としての記録と調査はかかわる人々の行動や記憶を触発し、それは記録や調査を行う人々との関係づくりに寄与することにもなります。いつしか「種は船」に対して「船は種」と名づけたように「図と地を反転させる」行為の連鎖が舞鶴の地で生まれることにもなりました。

「記録は、プロジェクトの2次的な、付随的な行為なのではなく、アートプロジェクトに、そもそも記録調査が組みこまれているべきだという発想の転換、視点の転換を試みた」*3。
*3:『アートプロジェクトのつかまえかた』、54頁。本記事には記録と調査をする人と「現場との距離感」も話題として収録している。
こうした考えをもとにした「船は種」の経験からは、従来は拾いづらかった「飛び火効果」ともいえる派生効果を記録するのみならず、この記録と調査という「行為」がプロジェクトにかかわる人々を触発し、プロジェクトの幅や成果を増幅させることがありうるのだとわかりました。記録や調査の活動は、実践の価値を跡づけるだけではなく、プロジェクトの豊かさを高める効果をもつのだと思います。
むすんで、ひらく|「第3コーナー」と公共性
最後に、本当は最初に問うべきことを考えたいと思います。
なぜ「第3コーナー」の活動に取り組む必要があるのでしょうか?
「第3コーナー」の活動がアートプロジェクトの現場で後回しになってしまう理由は容易に想像できます。記録やアーカイブ、調査に検証、報告と評価など、こうした言葉を聞くだけで作業の大変さが思い浮かびます。ただでさえも準備から実施までが忙しい現場で、そうした活動を実践することは困難なことです。時間もコストもかかります。スキルも足りない。人もいない…。やりたいけれどやれない理由は山積みです。
一方で「アーカイブ」や「評価」に対する社会的な関心は高まるばかりです。だからといって「やらなければならない」と自分なりの必然性を持たずに始めてしまうと、これほど辛い作業はありません。必然性を理解し、スキルをもった専門家に頼めば、ある程度は回避できる問題ですが、資源の限られたアートプロジェクトの現場では専門的なスキルを持たない人々が作業を行うことが多いのも事実です(もちろん、専門家と組むことや、そのための資源確保の意義はいうまでもありません)。だからこそ、「第3コーナー」の活動を進めるためには、作業で手を動かす人のそれぞれが、この「なぜ」に対して自分なりの理由をもっておくことが大事になってくるのだと思います。
「第3コーナー」にこだわる、一つの理由は(急に大きなことばを使いますが)自らの実践の「公共性」を意識するかにかかっているのだと思います。いまだ出会ったことのない人、もしくは、きっと出会うことのない人々に対する想像力をもち、そこにプロジェクトの価値を届けることを考えるかどうか。公的な資金を使っているかどうかは関係ありません。むしろ、どれほど私的な(ように見える)活動であったとしても、それを「公」の領域に掬い上げることがアートプロジェクトを実践する意義であるのだと思います。
実践の場で生まれる価値に参加者がきちんと出会えるように適正規模で場を「閉じる」こと、そして、その場に立ち会わなかった(立ち会えなかった)人々に向けて価値を「開く」ことを試みること。この両面があることで、ひとつの「現場」が、本当の意味で完結した円を描いたといえるのではないでしょうか。「第3コーナー」について考えることは、なぜ、誰にプロジェクトを仕掛けているのか? という自らの実践の射程を問うことになるのだと思います。

(2018年2月2日)
お知らせ
おすすめの1冊
-
『コミュニティ・アーカイブをつくろう!──せんだいメディアテーク「3がつ11にちをわすれないためにセンター」奮闘記』
佐藤知久・甲斐賢治・北野央著、晶文社、2018年。東日本大震災の記録を市民が自らの手で残し、発信するプラットフォームとして2011年5月3日に立ち上がった「3がつ11にちをわすれないためにセンター」(通称:わすレン!)。「わすレン!」を「コミュニティ・アーカイブ」の活動と位置づけ、その現代的な意義や理念、そして実践の試行錯誤や活動に参加した当事者の声などが収録されています。記録の「活動」づくりを実践するための示唆に富んだ厚みのある1冊です。「船は種」に関わったNPO remoと地続きの活動であることも記されています。
-
『僕と演劇と夢の遊眠社』
高萩宏著、日本経済新聞出版社、2009年。数十年先に、いまの実践をこれほど精緻に記述できるだろうか? そのための記録をちゃんと残せているだろうか? 何とか脅威の記憶力を身につけてみようか…とまでは思いませんが、金額、日数、人数など具体的な数字とともに語られる、かつての実践の軌跡を読みながら、つい、どう書いたのか(書けるのか)を考えさせられます。いうまでもなく内容は、ずばり、アートマネジメントです。
-
Web展覧会「木下直之(を)全(ぶ)集(める)」
ギャラリーエークワッドの特設ページ、2017年~更新中。そうか、こういう方法があったのか、と思わず膝を打ってしまいます。過去の著作12冊(と幻の1冊)を全13巻の全集に見立てて、ギャラリーで展覧会を開催する。会期は2018年12月から翌年2月まで。これは、その1年前から始まったWeb展覧会。ウェブサイトの更新性を上手く使って、(半)定期的にコンテンツを追加し、一年をかけて成長していく設計になっています。今回の記事としては、全集の第4巻(隠れた)名著の『世の途中で隠されていることー近代日本の記憶』もおすすめです。