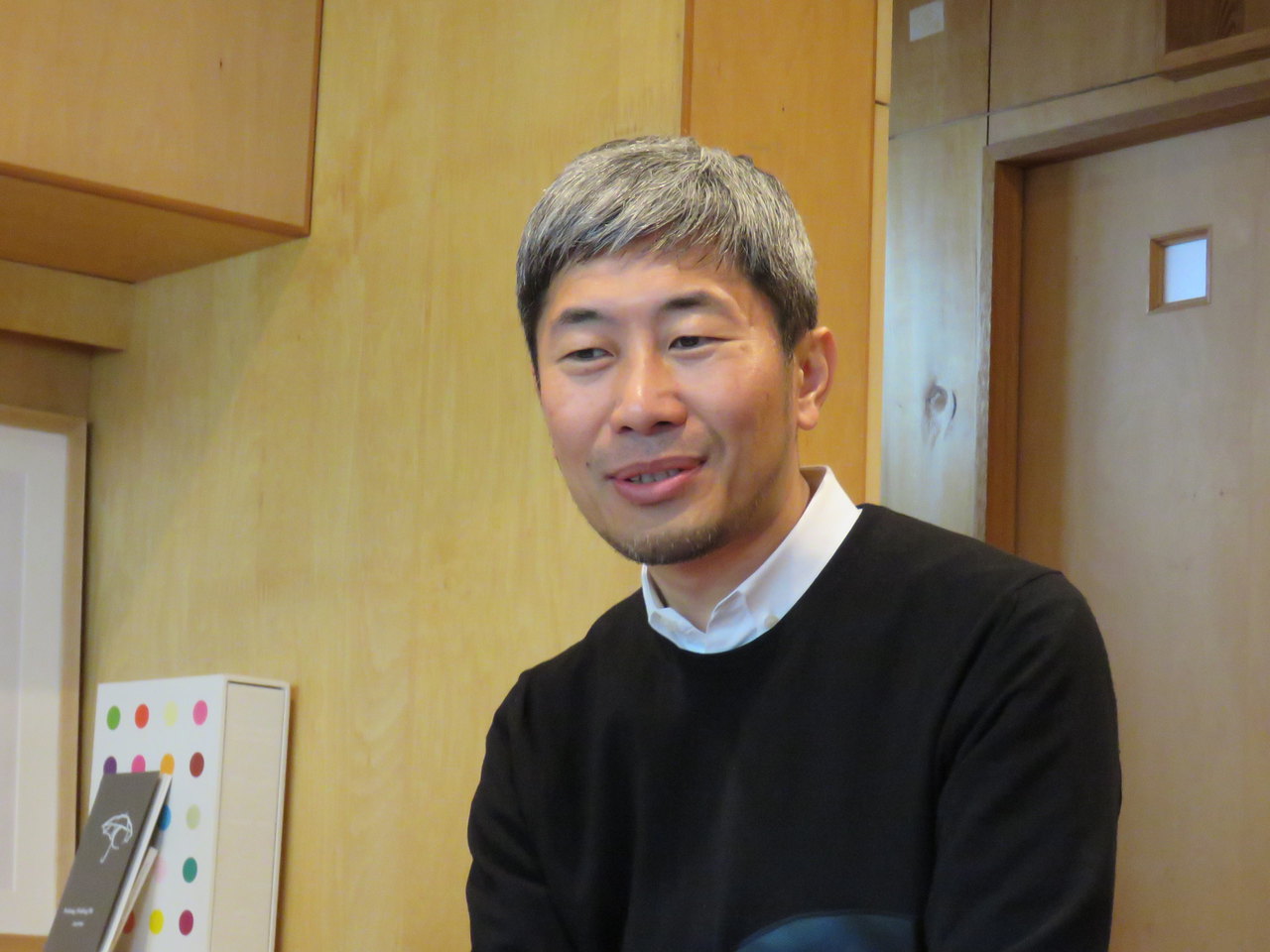本とクルマは、なぜアートに近づくのか?

クルマをとりまく文化、またアートとの接点を探る、今回のスーパーバイザーであるトヨタ博物館長の布垣直昭氏によるリレーコラム。
第2、3回は、同博物館にあるブックカフェの選書を担当し、日本随一の“ブックディレクター”幅允孝氏との対談をお送りします。
テーマは「本とクルマは、なぜアートに近づくのか」。話はカフェの小さな本棚から、進化するモビリティと本というメディアの課題と、未来像にまで広がります。
雑多な本棚から垣間みえるクルマだから生まれる物語
──『トヨタ博物館』にあるカフェ「CAR&BOOKS」のセレクト。幅さんはどんな観点でなされたのか、あらためて教えてもらえますか?
幅允孝(以下・幅):はい。「CAR&BOOKS」は、博物館内の濃密なクルマの展示を終えて最後にたどり着く場所にあります。だから足を踏み入れた方には、まずふっとリラックスしてほしかった。そこにある本もいかにもクルマのマニアックな書籍だけじゃなく、硬軟織り交ぜた幅広いジャンルを置きたいと考えました。
布垣直昭(以下・布垣):その“幅広なジャンル”を象徴するのが『ちびまる子ちゃん』でしょうね。もしかしたらカフェで最も読まれているかもしれません(笑)。
幅:「わたしの好きな歌」という映画の描き下ろし原作本ですね。花輪くんが自分の執事が運転するロールス・ロイスにまる子を乗せて「人生で一度、君もロールス・ロイスを味わってくれたまえ」というシーンがある。
布垣:おもしろいのが『ちびまる子ちゃん』のすぐ横にロールス・ロイスの工房をスタイリッシュに切り取った大判写真集があること。このカフェでしかありえない本棚で、気に入っています。
幅:コト・ボロフォという南アフリカ出身の写真家の作品です。彼はエルメスの職人たちなどアルチザンをとても美しく撮ってきた人。同じ手法でロールス・ロイスの工場の職人を撮り、ていねいに木やレザーといった自然素材を使い、手仕事で仕上げている様子を見せてくれる。クルマを通して、モノづくりのプロセスの美しさ、素晴らしさを伝える写真集だと思います。
トヨタ博物館内の「CAR&BOOKS」に置かれている幅氏による選書の一部
──『100万回生きたねこ』で知られる絵本作家の佐野洋子さんのエッセイがあるのは?
幅:『死ぬ気まんまん』ですね。佐野さんは晩年がんが転移して余命2年と告げられます。それでもウィットに富んだ日々を過ごした彼女の日常が書かれているのですが、がん宣告されたその日、最後の物欲としてイングリッシュ・グリーンのジャガーを買うくだりがある。
「私は国粋主義でクルマもずっと国産だったけど、実はグリーンのジャガーが最も美しいと思っていた」と告白してね。しかも、それを喫煙室として使ってしまうという豪快さです(笑)。
布垣:贅沢ですね(笑)。そのギャップにおかしみがある一方で、歴史あるクルマが持つ意匠としての美しさや、憧れを抱かせるようなブランドの価値が、逆に照射されやすいですよね。
幅:おっしゃる通りです。クルマは移動手段として使う乗り物です。しかし、同時に大きな産業でもあるし、長い歴史をはらんでいるし、クルマを通して培われた技術、デザイン、ビジネスなど、実に多彩な文化を育む起点でもありました。
本を通して、そうしたちょっと違った角度から見えるクルマと、クルマの周辺の奥深い物語を記憶して持ち帰っていただけたら、棚をつくった者としてはうれしいですね。
布垣:この4月、博物館内に起ち上げた『クルマ文化資料室』のねらいもまさにそれです。クルマ以外の展示によってクルマあるいはモビリティがとりまく豊かな物語、文化を伝える場にしたい。
たとえば展示してある本の“挿絵”をみると、文化の変遷がわかるような感じです。
幅:ほう。
布垣:馬車が描かれたころの本と、世界で初めて自動車が走り始めたころの本。それぞれで「貴婦人が描かれた挿絵」があります。これを見るとあきらかに髪型が違う。
モビリティとして馬車を使っていたころは、大仰なエレガントな髪型や帽子をかぶっている。しかし、自動車になると風の影響が強くなるので髪型はコンパクトになり、身分の高い女性なのにマスクまでつけている挿絵まであるんです。
幅:おもしろい。移動手段が変わったことで生活スタイルや文化も変わった。ファッションのような流行まで変えていると。
布垣:クルマが文化を生み出すことをわかりやすく伝えますね。こうした重層的な魅力こそ、クルマの大きな魅力でもあるのでしょう。
幅氏
クルマがクルマではなくなるとき文化は消えるのではないか?
──一方で馬車からクルマに変わった以上のパラダイム・シフトが、自動運転などの普及で起ころうとしています。クルマ文化はどのように変わっていくと思われますか?
幅:クルマがクルマじゃなくなる世界が来るかもしれませんよね。A地点からB地点に移動するとき黙っていてもAIが最短距離を導き出して、快適な居住空間のような乗り物に入れ、僕らを連れて行ってくれるような……。
唐突ですが、先日、仕事の関係でフェラーリのポルトフィーノを借りて何日間か運転させてもらったんですよ。
布垣:フェラ―リですか。すこし幅さんのイメージと…。
幅:違いますよね。だから「赤以外でお願いします」と色だけは指定させてもらいました(笑)。最初はスポーツカーなんてほとんど運転したことがないし、音も派手だし、おっかなびっくり。ただ運転するうちに、段々気持ちが高揚していくのがわかるんですよ。
アクセルを踏み込むと心地よく加速し、止めたいところですっと止まる。ステアリングのクセもつかんで…4日めには、クルマが自分の拡張された身体のような感覚になっていた。
布垣:わかります。クルマの運転は得もいわれぬ没入感、楽しさって、ありますよね。
幅:ええ。こうしたクルマが持つ「プロセスの楽しみ」が、自動運転が普及するとなくなっていく。ただただAとBの点と点を結ぶことこそに価値が置かれ、その間のプロセスがスポイルされる。「運転の楽しさ」はもちろん、先に述べたようなファッションや流行にまでつながる「豊かな周辺文化」のようなものも問われなくなるのかな、という気はします。
布垣:変わるところはあるでしょうね。ただ、変わらないところもあるのではないですか。先程の写真集のような「手作業によるていねいなつくり込み」みたいなことは確実に残る。
たとえば我々トヨタのようなクルマメーカーが「ドアの閉まる音ひとつまでこだわる」ようなつくり込み。それは自動運転になっても変わらず続けていくべきことだろうと思っています。そのプロセスに宿る文化は、形は変わってもまた残っていく気がする。
そうした仕事がクルマ、モビリティの“味“になり、さきほど幅さんがおっしゃったような、運転の楽しみに近い、何かを残すのかなあと。
幅:そうか。たとえば店舗のスタイルは効率性を求めて回転寿司のようになった。けれど、寿司の美味しさはやはり、ネタの新鮮さや、ていねいな包丁の入れ方だったりする。それに近いのかもしれませんね。
布垣氏
デジタルと紙の本の違いはそこに宿った「怨念」の差
──ところで、本の世界はモビリティの変化よりも早く、デジタル化によって進化、変化が進んでいますね。
幅:本も雑誌も紙ではなく、タブレットやスマホで読む人が増えましたね。ただ並走するように紙の本も残っている。
では紙の本とデジタルのテキストの違いは何か、といえば「アップデートできる—できない」に尽きるんですね。当たり前ですが、電子書籍やウェブサイトはアップしたあとに間違いがあっても、修正できます。
しかし、本や書籍は「校了」というものがあって、原稿を入れて、レイアウトを組んだものを、印刷したら最後、基本的には書き直せません。だからもう何度も何度も推敲するわけです。
布垣:そうですね。私も昨年、本づくりを手がけたので、その苦労が分かります(笑)。
幅:情報に間違いはないか、この表現で読者に伝わるか、助詞を「が」にするか「を」にするか、文章のリズムはどうか、写真はこれが適切なのか、フォントは、レイアウトは読みやすいか──。
一度刷ったらアップデートできないからこそ、こうした推敲、つくり込みが、よりなされる。それが単に誤字や脱字がない、情報として正しいだけではなく、コンテンツとしての“精度“や“強度”となって染み込んでいく気がします。
布垣:なるほど。これもつくり込み。本の“味”になっていくのかもしれないですね。
幅:そう。私はそこに奇妙な「怨念が宿る」と表現しています。
布垣:怨念(笑)。
幅:ええ。そうしたよい意味での怨念や人間の痕跡が宿ったプロダクト、コンテンツというのは人の心を深くつかみ、文化と呼ぶにふさわしいストックになるのかなと感じています。
布垣:わかりますね。先述どおり『トヨタ文化資料室』には、19世紀のモーターショーのポスターやカタログ、ノベルティやおもちゃなどの資料が数千におよぶ数があります。そのどれもが、ある意味不必要にエネルギーに満ちあふれたつくり込みを感じさせるんですね。だからこそ、100年たったいま触れて、見て、興味深い。
幅:怨念ですよ、まさに。「伝わってほしい」「もっと理解してもらうにはどうすれば?」というつくり込みが、あったんでしょうね。
裏返すと、本でもクルマでも。紙でもデジタルでも。そんなつくり込みの労力を割けられるか、エネルギーを捧げられるか。そうした部分がモノづくりや場づくり、コンテンツづくりにおいて、とても大事になってくる気がします。
AIが進化してシンギュラリティといわれる分岐点が間近に迫ったこれからは、なお。
またそういう意味で、僕は人間の「五感」に注目すべきかなと感じています。
布垣:「五感」ですか?
──後編へ続く。
- 取材日:2019年4月9日
- 取材地:有限会社BACH(バッハ)
- 取材・文:箱田 高樹(株式会社カデナクリエイト)
- 協力:トヨタ博物館