研究と現場/研究の現場
「現場」とは何か?-研究者らしく問いを立てる
「文化政策研究とアートマネジメントの現場」という連載テーマを小林真理先生(第1回)からお聞きして、最終回の担当なのに早くも秋口から考え込んでしまった。
私にとって、「現場」とは一体どこを指すのだろうか。
以下本論文、じゃなかった本コラムでは、私自身を事例として、「現場」とは何かという問いについて、3つの仮説をもとに考察してみたい。
仮説①:現場=具体的な活動
現場=具体的な活動という説明はシンプルでわかりやすい。個別具体的な事例の話には、現場ならではの実感が伴う。実際に日本の文化政策やアートマネジメントは、現場の先進的な活動の積み重ねで発展してきたとも思う。
翻って私の研究の核にあるのは、「文化権(cultural right)」の理念である。理念なので「抽象的」にならざるをえない。文化権は、第二次世界大戦後に世界人権宣言第27条や国際人権規約A規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)第15条に謳われて国際社会で議論されるようになった、比較的新しい人権である。創造や享受をはじめさまざまなかたちで文化にかかわりを持つことは、一部の恵まれた人間のみに認められる特権や贅沢ではなく、人間である以上当然に望んでいいはずだ、というのが、文化権の理念の根底にある問題意識である。
文化権は、「文化」という概念の多義性・多様性を背景に、他の人権と比べて議論が遅れがちだったため、今なお議論が続く発展途上の分野でもある。博士論文では、日本における文化権の理論研究を憲法と接続させたいと思い、従来は社会保障分野ばかりで用いられてきた日本国憲法第25条第1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」に着目した。そもそもなぜ第25条で「文化」という言葉が用いられたのか。その思想的・歴史的背景を検証し、文化政策における文化権の保障と第25条の「文化」を関連づける可能性は開かれていることを明らかにしたのが、通算10年以上かかった博士論文の研究成果である。こうした抽象的な理論を具体的な現場での活動とどのように接続させていくかは、私自身の今後の研究課題でもある。

アートNPOとして福祉やまちづくりに取り組んでいる認定NPO法人クリエイティブサポートレッツの「たけし文化センター連尺町」開所式の様子。開館にあたって部分的に協力した経済産業省補助事業「浜松市連尺町を中心としたソーシャル・インクルージョンによる拠点形成に向けた調査事業」は、昨年末に日本アートマネジメント学会の発表で紹介した。レッツの活動を文化権の理念と関連づけてきちんと論じるのも、今後やりたい研究の一つである。(筆者撮影)
仮説②:現場=文化政策やアートマネジメントの実践
現場=文化政策やアートマネジメントの実践という説明も、理論との対比でわかりやすい。そのような実践の現場に対しては、外部の専門家としてのかかわりになる。たとえば、アドバイザーや審議会の委員として自治体文化政策の議論に参加する。最近では、実践にかかわる方々の研修の講師という機会もいただけるようになった。
外部の専門家として発言するときは、今この現場でこういう実践を行うことが、文化政策やアートマネジメントの分野全体の大きな流れの中でどのような意味を持ちうるか、現場の方々に伝えられるよう心掛けている(うまくいくときも、思うようにいえないときもあるが、心掛けてはいる)。人権尊重を掲げるオリンピック開催を前に、文化政策におけるソーシャル・インクルージョン(社会包摂あるいは社会的包摂)に注目が集まり、社会全体においても国連の持続可能な開発目標(SDGs)が重視される時代にあっては、文化権の実現から取り残される人を出さないようにすることが求められる。政策担当者やアートマネジャーには、文化権実現の担い手としての役割が期待されている。その認識の有無で、実践のディティールは大きく変わってくるだろう。
このような外部の専門家としてのかかわり方は、現場の当事者のかかわりと比較して、意味合いが大きく違うことは間違いない。あくまで「よそ者」としてのかかわりだといえる。
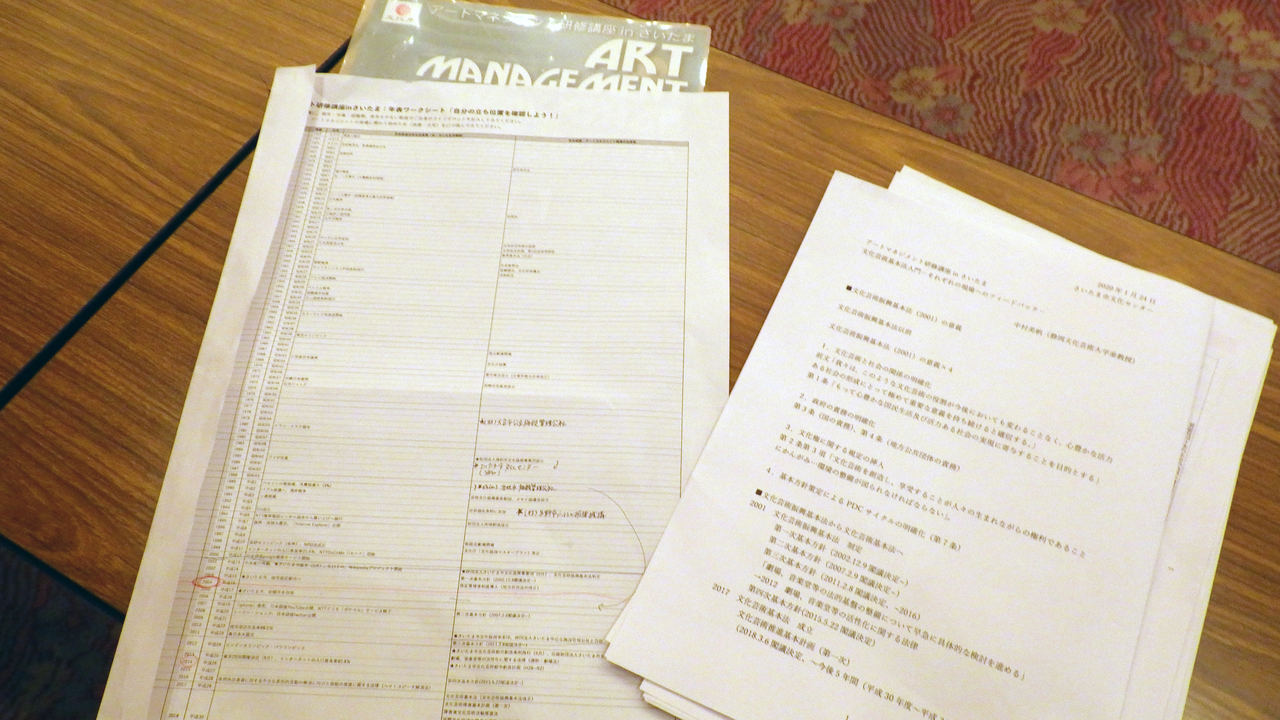
1月にさいたま市文化センターで開催した「アートマネジメント研修講座inさいたま 文化芸術基本法入門-それぞれの現場へのフィードバック-」で初めて使用した年表型ワークシート。さいたま市文化センターは、昨年12月の日本文化政策学会研究大会の共催先としてお世話になり、見知ったスタッフの方々が受講生として参加されることもわかっていたので、思い切って使ってみた。とても小さな字になってしまったけれど、ベテランと思しき参加者が、ご自身の職歴をたくさん書き込んでグループディスカッションで発言している様子は、見ているこちらもうれしかった。(筆者撮影)
仮説③:現場=自身の勤務先
さらに明瞭で手っ取り早い説明として、現場=自身の勤務先というアイディアはどうだろうか。私の場合、それは大学である。
本務校である静岡文化芸術大学は、2000年4月の開学にあたり、日本で初めての文化政策学部を設置した。国の文化政策の基本法となる文化芸術振興基本法(旧法)が制定されたのは、翌2001年12月のことである。静岡県西部の浜松市に立地する地方公立大学だが、2007年には日本文化政策学会の設立総会が開催され、2017年には日本文化政策学会第10回研究大会「文化政策の新たなかたち」、2018年には日本アートマネジメント学会第20回全国大会「アートマネジメントの20年」も開催されたように、まさに日本の文化政策・アートマネジメントの進展とともに歩み、その議論を支えた研究機関だといえる。大会時には開催校スタッフとして議論の場の運営に奔走するのも、広義の研究者の仕事である。
大学は、研究機関であると同時に教育機関でもある。静岡文化芸術大学文化政策学部の中でも私が所属している芸術文化学科は、2010年に芸術経営教育者協会(Association of Arts Administration Educators、AAAE)に正会員として加盟するなど、アートマネジメント教育に力を入れてきた。文化権に限った話でもないが、抽象的な理念を現実に実現させるのは、それを大切に思う一人一人の人間の具体的な行動である。よって、理念の実現に向けて教育の果たす役割は大きい。結果として実践の現場に就職しなかったとしても、文化政策やアートマネジメントを学んだ人間が社会に増えていけば、文化や芸術のあり方も豊かに広がっていくはずだ・・・授業の準備や学生の指導、学期末の採点や入試業務など、教育の現場としての仕事が忙しいときこそ忘れてはいけないと、自戒を込めて思う。

2019年度は中村ゼミ4期生4名が無事卒論を提出した。学生には「先生が笑顔で(卒論の)ハードルを上げていくのが恐い」といわれたことがある。今年度は諸事情で恒例の忘年会が開催できなかったので、提出おつかれお茶会のケーキを豪華にしたら、買い出しの3年生が素敵なプレートも調達してくれた。これまで送り出した1~3期生計13名の卒業生達は、元気に楽しく暮らしているだろうか。(学生撮影)
考察:研究者にとっての「現場」とは
「現場」のとらえ方は、私一人を例にとっても実に多様である。私に限らず、これまでの連載(第2回・第3回・第4回・第5回)をみても、現場のとらえ方は研究者によって大きく異なる。研究者にとって「現場」とは一体何なのか。
2020年の正月に、アートに限らずさまざまな現場でのしなやかな活動を尊敬している知人からの年賀状で、「時々美帆さんの知的な(俯瞰した)コメントが恋しくなります!」という、大変光栄なメッセージを頂戴することができた。ご本人の許可を得て私信から引用させていただいた、この「知的な(俯瞰した)」という表現は、現場に対する研究という営みの特徴を端的に現していると思う。
研究者は「現場」にかかわるが、「現場」と一体化することはない。研究者と現場の関係は、「よそ者」「他者性」を残したかかわりになる。現場の方々に敬意を持ちつつ、どこかで距離を保って考察の対象とする。研究者が、現場で当事者として頑張っている方々とは、根本的に立場が異なる所以である。
そのような研究者の視点の取り方は、中立的にいえば「俯瞰した」見方だが、「上から目線」と批判される可能性と隣り合わせでもある。しかしそうやって得られた発見が、いつか何かのかたちで誰かの役に立てば、それが研究による社会貢献といえるのだろう。研究成果がいつ何処で具体的な現場の支えになるか、研究の時点ではわからないことが多い。「抽象的」な理論研究の場合は、尚更である。それでも、上から俯瞰することで初めてわかる発見を探求するのが、研究者の仕事だと私は思う。
だから研究という立場からは、何処だって現場になりうる。論文執筆にかかわる場面はもちろんのこと、学識経験者として出向いた先も、大学教育や学会運営に追われる日々も、プライベートな週末の地域活動や家族のケアさえも、すべてが研究の現場たりうる。
研究者と現場の関係は、個々の研究者と個々の現場次第で、多様な可能性に開かれている。
関連リンク
1.法令について
- 電子政府の総合窓口e-gov法令検索
日本国憲法、文化芸術基本法など、日本国内の現行の法令の全文を見ることができます。 - 国際連合広報センター「世界人権宣言テキスト」
- 外務省「世界人権宣言」(仮訳文)
- 外務省「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」
- 文化庁「文化芸術振興基本法」
2.本コラムで取り上げた団体等について
おすすめ!
文化権についてもっと知りたい方は、この3つの文献をご参照ください。
小林真理『文化権の確立に向けて―文化振興法の国際比較と日本の現実』
勁草書房、2004年
中村美帆「文化権」小林真理編『文化政策の現在1 文化政策の思想』
東京大学出版会、2018年、103-118頁。
中村美帆「日本国憲法第25条「文化」概念の研究―文化権(cultural right)との関連性―」(東京大学大学院人文社会系研究科学位論文(博士)、2017年)要旨
浦河べてるの家の当事者研究
研究という視点を獲得することで生きることが楽になることもあると勇気をもらえます。
向谷地生良・浦河べてるの家『安心して絶望できる人生』(NHK出版、2006年)を読んで知りましたが、今回の執筆をきっかけに新版(向谷地生良・浦河べてるの家『新・安心して絶望できる人生 「当事者研究」という世界』一麦出版社、2018年)が出されていることを知り、取り寄せ中です。
品田知美『〈子育て法〉革命―親の主体性をとりもどす』
中公新書、2004年。
本書の研究成果を読了すると、育児書への向き合い方が変わる本。私自身も相当助けられただけでなく、出産を控えた女性研究職にプレゼントするたびに大変感謝され、研究は具体的に人生の役に立つと実感できます。
バトンタッチメッセージ
研究者にとって現場とは何かということをまさに中村美帆さんが真正面から捉えてくれました。研究者も研究者なりにつねに現場に対して何ができるかを真摯に問うています。とりわけ現実に日々さまざまな問題に直面している「現場」を見過ごすことはできません。それほどまでに文化政策やアートマネジメントを研究する者にとって、現場は現実です。一昔前、他の学問領域で研究者が現場に成果を還元しないことが問題になるようなこともありましたが、いま活躍している人たちにそういう意識の人たちはいないのではないでしょうか。具体的な現場の課題を改善したいと積極的に研究から貢献したいと考えていると思います。昨年は、あいちトリエンナーレで起きたことが大きな問題になったかと思えば、おりしもこのエッセイが掲載されている現在、新型コロナウィルスという感染症によって文化や芸術の現場が直接に大きな影響を受けています。政治的、経済的、環境的要因の影響を受けやすいこの領域。私たち研究者は、とにもかくにも「根拠」(エビデンス)を明らかにすることが求められます。それをどのような方法で示すかは、その研究へのアプローチの仕方でも異なります。即効的にウィルスの感染を止めたり、ワクチンを開発できたりはしないかもしれないので、現場の人たちからはもどかしく思われるかもしれませんが、現場の状況改善に向けて日夜併走している研究者たちがいるということも知ってほしいと思いました。まだまだ研究・調査しなければならない領域が広がっています。
(小林 真理/東京大学教授)


