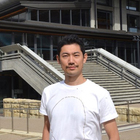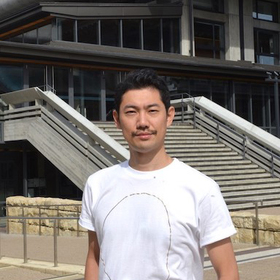TAMミーティング2020 アートの現場の“今”と“これから”について(演劇・舞踊編)
オンラインイベントレポート
芸術文化活動を応援するネットTAMでは、コロナ下での芸術活動や表現について"考える場"として、オンラインによるトークイベントを展開しています。
10月~11月の間、その第2弾として「アートの現場の"今"と"これから"について」と題したシリーズを実施。具体的に3つのジャンル(演劇・舞踊、音楽、美術)毎にオンラインミーティングを始めました。
初回は10月25日、「演劇・舞踊」から。郷土芸能、ダンス、そして公共ホールという各々の前線で活躍する3名の方々に、現場が抱えている課題と、変わらざるをえない未来について語っていただきました。
キャンセル数147件、年間損害額2億円近くの衝撃
新型コロナウイルスの感染拡大以降、社会システムも暮らしも、そして芸術文化もこれまでの有り様は、大きな変更を余儀なくされています。アートの現場において、その表現や活動はどう変わり、今後どうなっていくのか──。
それを探るため、モデレーターの若林朋子氏は最初のテーマとして「2020年、アートの現場に何が起きたか、起きているのか」を提示。セッションが始まりました。

小岩秀太郎氏
「私が理事を務める全日本郷土芸能協会の会員にアンケートをとったところ、92%の団体がコロナウイルス感染拡大で影響を受けた、と答えていた。つまりほぼすべてだ」と伝えるのは、全日本郷土芸能協会理事で、自身も岩手に伝わる鹿踊(ししおどり)の演者である小岩秀太郎氏です。
小岩:神楽や獅子舞など、日本はその名に地域名を冠した郷土芸能が数多く残る国。たいていは地域の"祭り"の際に披露されてきた。ところが、コロナ禍で祭りは軒並み中止になった。演じる機会が無くなり、そのまま消滅しそうな郷土芸能も少なくない。郷土芸能の担い手は、非常に過疎高齢化率が高いためだ。機会と意欲を奪われた彼らにとっては、継承のモチベーションの維持が難しくなっている。
演者のみならず、伝統芸能や郷土芸能につきものの和楽器奏者や、わらじや装束のつくり手も大きな打撃を受け、波及的な被害にも言及しました。
ダンサー兼振付師で、立教大学現代心理学部・映像身体学科の特任教授も務める砂連尾理氏は、ジャンルは違えど、同じ踊り手であるシンパシーとともに「お祭り同様、私もかかわっていた予定公演のほとんどがキャンセルとなり、厳しい状況が続いた」といいます。
砂連尾:ダンスは、人と接触したり、密になる代名詞のような行為。公演はもちろん、練習もままならない状況が続いている。文化庁の助成金に代表される資金援助でなんとか生計をたてているダンサーは多い。友人の映画監督がいっていた『ある地域の芸能あるいは踊りが無くなるということは、その地域の言葉が無くなることだ』という言葉が忘れられない。芸能が消えると、その周辺の文化がもろとも無くなる。大きな危機感を抱いている。

橋本裕介氏
ではダンス、演劇の舞台となる劇場は、どうだったのでしょうか。1960年に「京都会館」として開館し、2016年1月にリニューアルした劇場「ロームシアター京都」のプログラムディレクター、橋本裕介氏は「今年2月29日を皮切りに、新型コロナウイルスの影響による公演などホール利用のキャンセルが入り始め、今わかっているだけで147件のキャンセルが入った」と数字をあげて、事態の重みを際立たせました。
橋本:我々のような利用料制度を採っている公立文化施設の指定管理者は、施設利用料の収入が断たれると運営がきわめて厳しい。所属する財団は、ロームシアター京都以外にも指定管理をする他の京都市の文化施設があり、財団全体で今年度2億円に迫る損害額が試算されている。そのうえ弊館は6月26日に全国に先駆けてホールスタッフに感染者が出た。幸い迅速に対応でき、翌日から通常営業できたが、今も多くのリスクと損失を抱えながら運営しているのが現状だ。
オンラインが「芸能」のもつプリミティブな力を引き出す
こうした厳しい現況の中、舞台・舞踊の現場でDX(デジタル・トランスフォーメーション)の流れが急速に広がっています。
ウェブやオンライン・ミーティングツールを活用して郷土芸能は、ダンスはどう変わりつつあるか。テーマ2では「非接触時代のアート:芸術創造、アートプロジェクト、文化施設の活路」について議論されました。
2010年から高齢者施設向けにダンスワークショップを続けてきた砂連尾氏は、「オンラインがダンス、舞台芸術の本質に気づかせてくれた面がある」と指摘。
砂連尾:高齢者施設でのワークショップを6月からオンラインで再開した。これまでは『砂連尾先生どうぞ』と職員は僕に促すだけだったのが、今回はZoom越しに僕が職員の方に声がけして入居者の方へのダンスの振り付けを現場でお願いするというスタイルになった。結果として職員と入居者のふれあいが生まれて、より豊かなダンス、ケアができた。
遠隔操作でその場にいなくてもロボットを通して見聞きできる「分身ロボット」を手にし、重度障害者の方の目となり、耳となって9月の横浜トリエンナーレを見学するプロジェクトも実践。ダンサーならではの身体性をもって臨場感たっぷりに手に持ったロボットを操作することで分身ロボット利用者が「これまでも分身ロボットを使って現場に"行った"という感覚はあったが。今回は画面越しの砂連尾さんの展示物を触れる手の触感を通して"体感した"感覚があった」と評されたそうです。
砂連尾:接触しなくても触れあう感覚が味わえる。体験をシェアできる。オンラインを使った遠隔での体験をすることで、むしろダンサーや役者といった演者の身体性やスキルが、もっといろんな場所で違う役割を果たせるのではないかと考えた。思えば、我々演者はそもそも誰かの代わりに体験や情動を伝える"遠隔的な役割"がある。その技術を駆使して舞台表現をしてきたからこそ、非接触時代の媒介となりうる。そんな可能性を感じた。

砂連尾理氏
では、非接触の時代に、劇場はどのように立ち回れるのか。橋本氏はロームシアター京都がすでに手がけてきたいくつかの事例を紹介。
橋本:毎年8月に毎年ロームシアターで実施している『プレイ!シアター』という夏休みのイベントを、今年はオンライン上で展開した。くるりの岸田繁氏と角銅真実氏のライブや、「こどもディスコ」という企画、康本雅子さんのダンスワークショップなどを、YouTube、インスタライブ、ツイッターライブなど複数のチャンネルで、同時進行で配信した。リアルの場で行っていたように、お客さんに『劇場を移動して選ぶ』体験を楽しんでもらいたかった。オンラインだから体験できない、ではなくて『ライブ的な体験』を提供する方法はオンラインを含め多様にある。まだまだ考えていける余地があるのではないか。
ライブ感をもってオンラインで演目を提供する。橋本氏のこの話を受けて「それは他のアートジャンルでも共有し、考え、実践していきたい課題だ」とモデレーターの若林氏は提言していました。
その後、小岩氏はさらに本質的な「非接触によって郷土芸能の価値に気づかされた者は多いと思う」と発言。
小岩:ここ数十年、郷土芸能は『観客に見せる、集めるために演じる』ことに軸足を置いてきた面がある。けれど、そもそもは神や自然などの存在に対する祈祷・祈願などのために舞うことがルーツ。そこに観客の目は必ずしも必要なかった。祭りも舞台も集まっての練習もできづらくなった中で、いま個人や団体がひっそりと誰も呼ばずに舞い、踊っていたりする。そこであらためて郷土芸能が持つ、祈りの意味や意義を捉え直している当事者は少なくない。
それはかつて東日本大震災直後から、東北の郷土芸能の関係者が『誰かのなにかの役に立つかもしれない』と誰もいない場所で踊り始め、「地域の復興とともにどんどん復活していったことにも似ている」そうです。
非接触を余儀なくされたからこそ、あらためて芸術の本質と向き合い、気づく。意外な効能は、これから続くアフターコロナ時代の豊かな舞台芸術の礎にもなりそうです。
上意下達から、フラットな共犯関係に
最後のテーマは「変わるコロナ以降のアートマネジメント」。三者三様のアイデアが発せれられました。
まずロームシアター京都の橋本氏は「上意下達ではなく、水平型のマネジメントを」と提唱。
橋本:オンラインのツールは、誰しもアクセスしやすくフラットなつながりをつくりやすい。アートマネジメントに限らず、多くのプロジェクトは上意下達になりがちだが、水平なコミュニケーションがとてもしやすいオンラインに可能性を感じる。私が理事を務めているON-PAM(NPO法人舞台芸術制作者オープンネットワーク)での最近の例だが、障害を持っている方が劇場にアクセスしやすくするための活動をしている『NPO法人シアターアクセシビリティネットワーク』の廣川さんという方は、『イベント・ミーティングをオンラインでやるなら画面に字幕が出せるアプリがあるので、それを使えないか。これまでアクセスできなかった方の声が集まるはず』と提案してくれた。それをすぐに会員イベントで導入した。こうしたつながりをフラットにして、より開かれた活動が生まれる可能性が広がるはず。
話を受けて、小岩氏は「世代、時代のつながりも意識したい」と発言。
小岩:郷土芸能の世界でいうと、戦中戦後に活躍してきた世代と、今の40代くらいを中心とした世代、さらに20代くらいの次の世代で上意下達になりすぎて、断絶することがありえる。オンラインツールや映像化してデジタルで残すことも含めて、上と下も左右もつなぐ、縦糸と横糸を紡いでいくような意識がより必要になってくるのではないか。また世代だけではなく、先人から受け継いだ郷土芸能を次の時代へと残していくためにも、試されている気がする。
砂連尾氏は、大学の講義で若い学生たちに伝える言葉を話してくれました。
砂連尾:何をするにもどう判断して、どう動けばいいかわからない時代になっている。だからこそ『ソーシャルディスタンスなど政府が提唱するガイドラインに盲目的に従うのではなく、どう振る舞っていくかを自ら考えて、学びの機会にしてください』と伝えている。上意下達の話があったが、政策や団体や個人、あるいは芸術のジャンルなども超えてあらゆる表現者それぞれがどう振る舞うかを考えながら、互いに連携する。そんな共同関係、共犯関係を通してどのように信頼関係をつくっていけるのかが、ある種の新しいアートマネジメントのかたちになるのでは。
ジャンルを超えた共犯関係を──。
コロナウイルス感染拡大という状況だからこそ生まれた芸術の新たな可能性を共有してセッションは終了。次回から続く、「音楽」「美術」ジャンルにも共鳴するような、ヒントと希望が見える90分でした。
TAMミーティング2020【演劇・舞踊編】イベントアーカイブ
JAMボード(ことばの記録)Google jambordを見る⇒
(2020年11月11日)
取材・文:箱田 高樹(株式会社カデナクリエイト)